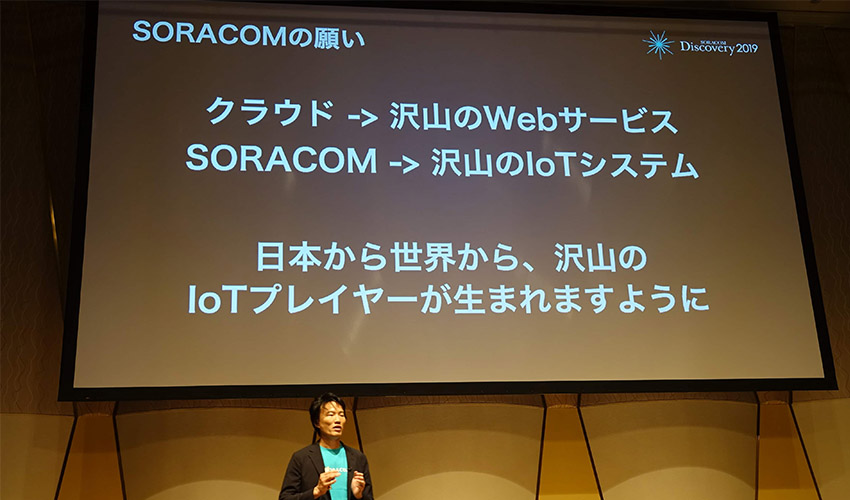今年も、ソラコムがその年次イベントDiscoveryを開催した。
先日回線数が100万回線を超えたというニュースを発表し、15,000社以上のユーザ、116社にも上る認定パートナーネットワークを作り上げてきた同社。
毎年、多くの関係企業が集まり、IoT黎明期から携わっている私は、IoTの今年はどうなる?というのを占う場としても注目している。
というのも、同社の2週間に一回はリリースされると言われる機能群は、顧客の課題やニーズを満たすために作られているからなのだ。つまり、ソラコムのプラットフォームに実装される機能は、とある企業の解決したい課題であり、「IoTの民主化」を進める同社からすれば、いかに技術的な苦労を強いることなくIoTサービスを実現できるようにするか、という命題に対する挑戦でもあるのだ。
そういう目でこの年次イベントを見ていくと、IoTの今と未来が見えてくる。
レポートの第一弾は、基調講演のレポートだが、内容が盛りだくさんなので、複数回に分けてレポートする。
ソラコムのプラットフォームが活用される産業分野
ソラコムのサービスで、まず一番使われているサービスといえば、SORACOM Airだろう。
当初SIMカードを提供し、SORACOM SIMを入れたデバイスは、ソラコムの規定する価格で通信サービスを利用することができる。
ご存知の方も多いかもしれないが、SORACOMのサービスでは、通常通信キャリアにしかできないことが管理画面で実現されているのだ。例えば、スピードの変更やSIMのアクティベート、SIM一つ一つの管理など様々なことを利用者側で設定できる。
これができることで、事業者は多くのデバイスに対して通信を活用する際に、ある意味「遠慮なく」通信環境を構築できるのだ。
今回、代表取締役社長の玉川憲氏は、「ソラコムはホリゾンタルと呼んでいる業界を問わない利用をすすめている」と述べ、6つの産業分野での利用を紹介した。
- 動態管理
- 遠隔監視・M2M
- 決済端末
- 工場の可視化
- 農業・漁業・畜産
- コンシューマー
これらの利用シーンは、IoTでは他の事例でも紹介されることが多い分野で、馴染みが深いのではないだろうか。一方、最近登場してきたものとして、3つの領域が紹介された。
一つ目が、プロダクトが登場した時から、通信が入っているコンシューマプロダクトが登場してきている。例えば、「POCKETALK」「LOVOT」「DFree」などだ。
二つ目が、シェアリングエコノミーだ。様々なリソースを所有するのではなく、共有する、それには、「誰が使っているのか」「どこで使っているのか」「どれくらい使われているのか」を知る必要がある。この事例としては、「メルチャリ」「eスクーター」「mocha(バッテリーのシェアリングサービス)」などが紹介された。
そして、三つ目が、リカーリングモデルへの利用だ。「Slat(ウオーターサーバ)」での離脱防止策や、「ふくやのたらこ」での自動発注の事例などが紹介された。
これらの事例は、IoTがバズワードであった数年前には、イメージされていたこともあるが、実現されていなかったことで、IoTを活用して我々の暮らしを良くしよう、ビジネスを変革しようとした動きが実現してきたソリューションであるとも言える。
クルマの位置情報から、販売から納車までのリードタイムのコミュニケーションを強化
ここで、ダイハツ工業株式会社 くらしとクルマ研究所 所長 役員の生駒勝啓氏が登壇し、SORACOM搭載デバイスをクルマにとりつけ、GNSSを活用して1cm精度でクルマの位置を把握する取り組みが紹介された。
この取り組みの目的は、顧客がクルマを購入した際、納車までの期間に感じるワクワク感を楽しく感じてもらうことだ。クルマが工場で製造され、ディーラーに運ばれた後、カーナビなどのカー用品が追加され、顧客の手元に届くわけだが、この期間で「今クルマがどこまできているのか」「どういう状態なのか」がわかれば、例えば納車直前に「フロアマットをお好きな柄に変えませんか?」といったアップセルのコミュニケーションも可能になるのだという。
ところで、こういったIoTにおける通信の利用に関して、「事業での利用」を意識すると、単に通信料金が安ければ良いとはならない。機密情報が流れることを前提としたセキュリティへの対策や、取得データの可視化など、事業利用を前提とした機能など多くの配慮が必要となる。
2015年からこの3年半で、多くの機能が実装されてきたことをIoTNEWSも追いかけてきたが、IoT利用を想定した際の機能については、「主要な要望には大抵こたえてきているな」という感覚があった。
昨年のDiscoveryの後も、来年を(つまり今年のDiscovery)をイメージした際に、「今後はアプリケーション分野やエッジ領域に進出していくのかな」と思っていたものだ。
ところが、実際はもっと大きなことが構想され実現されていた。
「IoT SIM」それは、グローバルIoTプラットフォームへの進化
2016年にグローバルSIMをリリースして以来、130カ国を超える国と地域で使うことができる同社のサービスだが、海外でも活躍する企業における利用ニーズは高い。
例えば、フジテックでは、海外で使われるエレベーターの遠隔監視に採用していたり、フランスのGo4ioTという企業では農機等の盗難防止モニタリングアセットで使われているのだという。
そもそも、2015年にソラコムは、そのサービスを開始して以来、セルラー通信だけでなく、LoRa WANやSigfoxといった非認可帯域でのLPWAや、LTE-Mと呼ばれる認可帯域でのLPWA通信などのサービスも提供してきている。
これらのサービスはどの通信を使っても同一の管理画面で管理することができて、例えばLPWAだからといってセルラー通信とできることは同じということも特徴だ。
ネットワークの選択肢が多いということに関して、経緯的にも日本国内からスタートしたこともあり、NTTドコモの回線やKDDIの回線を使うことが前提で、グローバル対応に関してはローミングサービスが前提となっていた。
ところが、今回の発表では、これらの通信サービスは統合され、「IoT SIM」と名付けられた、SIMが1枚あれば、世界中でSORACOMのプラットフォームを利用できるようになり、価格も日本を含むほとんどの国で、1MBあたり0.02USDという低価格の通信を実現したのだ。
これは、グローバルで一つの価格、一つのサービスを提供していくという意思表示であり、ソラコムのサービスが「グローバルIoTプラットフォーム」となることを意味する。
さらに、eSIMの利用や、海外でもマルチキャリアに対応できるなど、利用企業の利便性を考慮しつつ低価格を実現している。
現在の事例としては、「POCKETALK」を提供するソースネクストの「FamilyDot」という製品が紹介された。これは、71カ国で利用でき、これを持っているだけで家族の居場所をスマートフォンで確認できるという製品だ。eSIM版のIoT SIMがつかわれているのだという。
これまでであれば、海外進出を考えた場合、各国の通信会社とそれぞれ契約をしなければならないだけでなく、それぞれの仕様を考慮したシステム開発も必要であったため、簡単に海外進出することはできなかった。
しかし、今回の利用価格でIoT SIMが提供開始されることで、小ロットからでも世界に向けてIoTデバイスを販売開始することができるのだ。Amazon.comなどのECサイトを活用すれば、例えばeSIMが搭載されたウエアラブルデバイスを開発し世界に向けて販売するというようなことがいとも簡単にできてしまうようになったということなのだ。
また、日本国内だけの利用の場合でも、1つのSIMでNTTドコモとKDDIの回線が利用可能となり、NTTドコモの回線を使うより、KDDI回線を使う方が1/10のコストで利用が可能になるということが発表された。
さらに、グローバルSIMを使う場合、これまでは「ランデブーポイント」と呼ばれるドイツの都市に一旦ネットワークを経由させて通信サービスを利用していた。この場合、例えば日本でグローバルSIMを使う時は、一旦ドイツを経由して通信をしていたため、若干の遅延が起きていたのだという。
そこで、IoT SIMでは、ランデブーポイントを日本と米国にも配置し、主要国での遅延を極小化する努力をしたということだ。
また、もともと管理画面で通信速度を変えることができるというSORACOMの特徴があったが、今回fastという設定で2Mbpsであったのを、「4xfast」という設定が可能となり、最大8Mbpsでの通信も可能となるという。
次ページは、「グローバルをスタンダードとしたSORACOM」
グローバルをスタンダードとしたSORACOM
私が今回の発表でもっとも大きいと感じたのは、これまでグローバルSIMとよばれていたサービスを、IoT SIMと呼び変えたことだ。
これは、ソラコムのSIM(物理的SIMであれ、eSIMであれ)があれば、世界中どこにいてもSORACOM IoTプラットフォームの恩恵を受けられる、すぐにIoTを活用したビジネスをスタートできる、ということを前提とした、国内視点からグローバル視点への「視点の切り替え」だとも言える。
現在、世界中で一つの価格帯でIoTプラットフォームを含む通信サービスを提供している通信サービス事業者は、ないのではないだろうか。
ソラコムの取り組みは、通信事業者の取り組むグローバルサービスに対して、「もう一歩先の取り組み」とも言えるのかもしれない。
基調講演の続きは後日公開いたします。