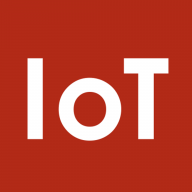2017年7月7日、IoTNEWSが主催する年次イベント「IoTConference2017 スマートファクトリーの今と未来」を大崎ブライトコアホールにて開催した。
午前中のセッションにて、IDC Japan株式会社 Worldwide IoT Team 鳥巣悠太 氏が「IoT Enabled Solution」がIoT市場拡大を牽引、製造業のとるべきアクションとは?と題して、「日本国内のIoT市場を全体俯瞰し、その現状に基づき、製造業のプレーヤはどういうアクションをとるべきか」について解説した。
IoTを取り巻く最新技術トレンド。データアグリゲーション、コグニティブ/AIシステムなど、先進技術の動向と展望
IDCでは、将来にかけてIoT市場が引き起こす下記の10大インパクトを発表している。
鳥巣氏は上記のスライドにおいて、緑で記されている4つのテクノロジーにフォーカスして解説を行った。
まず、IoTコネクティビティ、あるいはIoT通信は、2016年に全世界のIoTコネクション数は120億接続を数えたが、2025年までに800億IoT デバイスがネットワークにつながると予測されている。
その800億の接続には様々な通信技術が使われているが、LoRaやSigfoxなど、最近注目を集めてきたLPWA(低消費電力広域)技術は2025年までに1割を占めるようになり、日本国内ではすべてのIoTコネクションの3%に達すると予測している。
モバイル通信あるいは固定通信、信頼性あるいは経済性、各ユースケースに重視される通信技術の特徴に基づいて、IDCは下記の4象限チャートを作成した。
同チャートからの事例をみてみると、スマートメーターにおいてLPWA通信がすでに使われているが、スマートメーターの場合、すべてのコネクティビティがLPWAのみになるわけではない。例えば、920MHz帯がスマートメーターとスマートメーターの間データをバケツリレー方式の通信に使われるが、LTEのキャリアライセンスバンドを利用するあるいは電波が届かない場所ではPLC(電力線搬送通信)技術利用が適切だ。
これからはIoTに適した様々な技術が現われるはずだが、事例から分かる通り、各ユースケースやユーザニーズに合わせ、コネクティビティのメリットとデメリットを理解し、組み合わせて使うことは非常に重要になるという。
データアグリゲーションのインパクト
また、次の大きなインパクトとして紹介されたのはIDCが独自で提唱しているデータアグリゲーションの概念を解説した。
全世界、年間で生成されるデジタルデータ量では、2016年にIoTデータ(IoTデバイスのセンサが収集したデータ)の割合は非IoTデータ(企業システムにたまっているデータや人間が作り出すソーシャルなどのデータ)に比べると、非常に少なかったが、2025年までにIoTデータの急成長が期待される。2025年にも非IoTデータが8割を占めると予測されているが、これからはIoTと非IoTデータを組み合わせてアグリゲーションすることは重要になってくる。
データアグリゲーションによって新しいサービスが生まれた有名な事例としては、米国の航空エンジンメーカーGEがある。GEはIoTを航空サービスや航空オペレーションの最適化に活用し、全世界100の企業と同プログラムを実施している。このようなサービスの実現には、「非IoTデータ」が不可欠である。エンジン故障予測をしたい場合、エンジンの稼働分析が必要である一方で、燃費改善の場合、消費燃料データの収集と分析が必須となる。
一方で、航空機の部品交換の場合には、航空会社や航空機の整備会社の企業システムに入っている、航空部品データと整備員の配置データ(非IoTデータ)をアグリゲーションしていくことが必要になる。
上記の例と同様に、様々な産業ではデータアグリゲーションが今後広がっていくという。
鳥巣氏は製造業が色んなベンダーとデータアグリゲーションを進め、各産業にとがったソリューションを作り、産業特価型ビジネスをつくりだすという流れは加速していくと述べた。
コグニティブ・AIシステム
現在、コグニティブ技術・AIシステムが非常に注目を集めており、多数の企業が様々な製品やサービスを提供し始めている。
コグニティブ分野で活躍しているベンダーの動きでは2つの大きな傾向がある。
1つ目は、多数のIT・クラウドベンダーがコグニティブ・クラウド・プラットホームを提供し、ライブラリを強化するという動きだ。この動きによって、AI適用に付随しているコストや技術的な障害を乗り越え、ユーザーの裾野を拡大させているという。
2つ目は、半導体ベンダーによってAIチップのパフォーマンスが向上しているということだ。半導体ベンダーは機械学習に特化したチップを開発することで、コグニティブの利用パフォーマンスが劇的に向上させている。
しかし、コグニティブ分野にでもベンダーの製品やサービスを活かすためには、データが必要となる。
2016年まで医療の画像データをAIにより処理をしたり、金融業界の不正取引を分析する、などの事例があるが、ここでは主に非IoTデータが活用されていた。つまり、これまでは非IoTデータの利用によって、コスト削減、人的労働力を置き換えるという使い方がほとんどだった。
しかし、これからはIoTデータが爆発的に増えてきて、そのデータを特定の産業に閉じた形で使うのではなくて、データアグリゲーションによっていろんな産業にまたがって活用するケースが増加すると予測されている。
例えば、物流サプライチェーンデータは製造業だけではなくて、運輸業、卸売り業、小売り業、様々なサプライチェーンがまたがって、膨大なデータを共有することができる。
このようなデータをリアルタイムで収集し、コグニティブ技術で分析する。IoTとコグニティブ技術を組み合わせることによって人間にはできない判断スピードを創出されるという。
エッジ・コンピューティング
従来のIoTデータ分析・処理プロセスはローカルエッジ側で最大限で実施され、その後データをクラウドやデータセンターにあげ、そこでデータプロセシングを行っていた。
現在IDC はエッジコンピューティングを2種類に分けているという。
一つは「現場志向型エッジコンピューティング」で、クラウド側にほとんどデータを出せず、現場に閉じた形でエッジコンピューティングを実施するアプローチだ。このアプローチは主に医療現場でのエッジコンピューティングに採用されている。
現在、現場志向型エッジコンピューティングが増えている傾向が見られている。
その理由はデータを現場の外に出さなくてもいいことはユーザーに心理的な安心感を与え、さらにそのデータをクラウドにアップロードする時間やコストが削減できるからだ。
現場志向型エッジコンピューティングはIoTに対して保守的なユーザーが積極的に使い始めているという。
もう一つは「分散協調型エッジコンピューティング」であり、ローカルエリア内のエッジだけでなく、広域ネットワークのエッジも含まれる。
例えば、広域ネットワーク中で走っている自動車や交通システム、社会インフラシステム、広域ネットワークエッジを含めてクラウド側で分散コンピューティングをするといったものだ。
2020年までに、IoTデータの40%はエッジ側で処理/分析されると予測している。その40%のデータは分散協調型のエッジコンピューティングになるとIDCは考えていると述べた。
さらに、スマートシティや自動運転のようなIoTデータを爆発的に増やすユースケースが増えると、データ処理はエッジだけあるいはクラウド側だけではなく、両方を総合協調しながら使うことになる。
このことから、2020年までに分散協調型のエッジコンピューティングが真の力を発揮すると鳥巣氏は述べた。
次ページは、「自社のソリューションを外販できる、IoT Enabled Solutionの登場」
無料メルマガ会員に登録しませんか?
IoTNEWS代表
1973年生まれ。株式会社アールジーン代表取締役。
フジテレビ Live News α コメンテーター。J-WAVE TOKYO MORNING RADIO 記事解説。など。
大阪大学でニューロコンピューティングを学び、アクセンチュアなどのグローバルコンサルティングファームより現職。
著書に、「2時間でわかる図解IoTビジネス入門(あさ出版)」「顧客ともっとつながる(日経BP)」、YouTubeチャンネルに「小泉耕二の未来大学」がある。