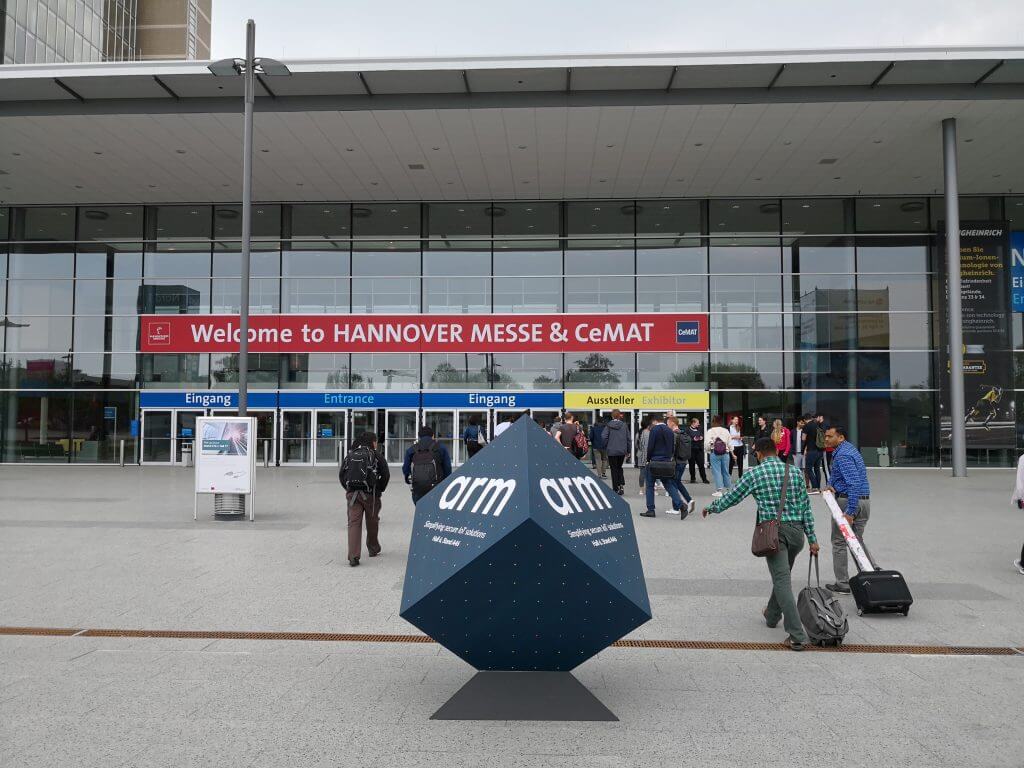ハノーバーメッセレポートの第8弾は、これまで様々な切り口で語られてきた、スマートファクトリーの現在と実際の展示に見る実現可能性についてだ。
4/23から開催されているハノーバーメッセ。今年も6,000社を超える出展があり、日本企業も100社弱が展示しているのだという。
国内のスマートファクトリーへの対応状況を見た時、果たして海外との差はあるのか、あるとしたらどういうところなのか、また、スマートファクトリーという概念はどこまで実現可能なのか、というあたりを整理したいと思いつつドイツ、ハノーバーへ向かった。
今回の記事は主に製造業の話題となるが、展示そのものとしては、エネルギー産業など様々な産業があり、さらには、ロジスティクス向けイベントも同時開催されていたので、すべてが見られたとは考えていない。しかし、業界の鍵となる企業を取材していく中で私が感じ取った「スマートファクトリーの今」をレポートできればと思う。
エッジヘビーへの対応
IoTが製造業において話題に上がり始めた頃、「工場の様々な状態をクラウドにアップロードするなんて無理」と言われてきた。多くの見解としては、そもそも秘密な情報が多い製造の現場の情報をインターネットになんかあげられない、という文脈だった。
しかし、それ自体は「なにもすべてのデータを上げなければならないとは思わない」と考えていた。
むしろ、工場内部で取得できるデータを全部クラウドにアップロードしたところで、そこから何が導き出されるのだろうか?いくら高速通信が実現できるようになったとはいえ、現場で起きた課題をIoTで検知して、クラウドで処理した後現場に戻すという考え方自体、非常に非効率だし、現場は現場付近で処理をしたほうがよい。
しかし、エッジヘビーの考え方が語られるようになって、多くのメディアが「エッジ側に閉じていた処理が、IoTによってクラウド側に移るとし、現実的にはエッジ側で処理せざるを得なくなってきてる」と報じている。事実を知ると、これは、ミスリードしている表現だと言える。
今回の展示では、生産現場に関するソリューションについて、多くの企業が産業機械に加速度センサーなどを取り付け、そのデータを取得し、エッジ付近に配置されたIPC(産業向けPC)などでデータ処理を行い、必要な制御を行う。といった展示になっていた。
ベッコフオートメーションやシーメンス、オムロンなど多くのIPCメーカーが、こう言った「エッジ側での処理」を当然のように展示していたのだ。さらに、後日詳解する、Microsoftなどはエッジ側にAzureと同じ挙動をするオンプレミスサーバを提供していた。
エッジ側のネットワークをどう考えるか
スマートファクトリーでは、産業機械をネットワークに接続することが前提となる。その際、そもそもネットワーク対応されている産業機械と、されていない旧型の機械で対応が分かれる。旧型のは「レトロフィット」と呼ばれていて、後付けセンサーを取り付けて情報を収集するという流れが国内外問わず明確になっていたと言える。
また、オムロンでは、配線に通る電流の変化を伝えるといったIO-Linkと呼ばれる技術も紹介されていた。
ネットワーク対応が完了してる産業機械については、それぞれのプロトコルが異なることが問題になる。
CC-Link, Profinet, EtherCAT, OPC-UA, TSN…様々な接続方式が登場する中、今年の展示としてはTSNに関する展示が目立った。(TSNについては別途シスコの記事にて詳解する)
TSNに期待がかかる理由としては、製造を自動化するという流れの中、既存のEthernetケーブルを使って、高速通信を実現するということが命題となってくるながれがあることが原因だろう。その一方で、TSNは設置の際にどのデータの伝送を保証し、どのデータは保証の対象からはずすか、といった設定が必要であることからネットワークへの期待が大きくなる一方で、既存の通信機器設置ベンダーは産業機械の挙動などについても知識と経験を持つことが重要になりそうだ。
また、ファーウェイを中心に、5Gに関する展示も散見された。ただし、5Gは必ずしも通信が保障されないということから、多くの関係者は「人と機械が協働するようなシーン」「遠隔地から産業機械に学習させる時のテーチング」「低遅延を生かした、即決断ができるための情報処理」というあたりのテーマで利用が進むという見解だ。
ネットワークのインターオペラビリティ(相互運用性)や、セキュリティの観点はプロトコルの話題と並んで重要なテーマとなっているが、ここについては後日、シスコのブース詳解の際に解説する。
産業用PCでどこまでの処理を行うのか
エッジヘビーという話題でも書いた通り、IPCの展示が多かったのだが、言ってしまえばPCなのだから何でもできるとなってしまう。小型で軽量なPCから大型で機械学習ができるようなものまで様々展示されていたが、これ自体は昨年も幾つかの企業で展示が行われていた。
今年注目したかったのは、処理能力の高いPCを利用することで、エッジ側で機械学習を行ったり、学習モデルを活用した柔軟な制御を行う展示だったが、これはオムロンの展示で見ることができた。
例えばマヨネーズのボトルキャップを締める工程で、きちんと締めることができない場合、それ自体を検知して一度ネジをゆるめ再度締め直すといったことを行うことで、製造そのものを止めないだけでなく、ロス率も下げることができるということが実現できるということであった。
また、以前の展示でも金型成形の際にAIを活用して切削精度を上げるという取り組みがあったが、今後、もっとエッジ側でのインテリジェントな制御が進んでいくだろう。
フレキシブルな生産と生産現場内の移動
マスカスタマイゼーションや多品種少量生産が言われる中、フレキシブルな生産が求められている。工場の中をモジュール化(産業機械と作業員をグループ化)し、必要な部材を運び込み生産し搬送する。
この流れの中で、コンピュータから指示を受け製造するようなロボット、そして製造現場に部材を運んだり製品を搬送したりするAGVと呼ばれる自動搬送機器もインテリジェントになり、これまでテープの引かれているところを指示に従って移動するだけであったものが、人や障害物を避けながら目的地に移動するというオムロンの展示や、マイクロソフトでは、さらに障害物の認識を画像認識で行い、荷物を積んでいるAGVを優先的に通す(道を譲る)といったことまでできるような展示も行われていた。
また、熟練工の技を継承するというテーマについても、多くの展示がされていた。多くは、ロボットの動作を人が手で教え込むやり方、機械学習をや画像認識を活用してロボットが自律的に動きを制御するやり方、そして、VRを活用した作業員の教育と、不慣れな技術者に対するARを活用した現場でのきめ細やかな作業指示などであった。
スマートファクトリーで生産性改善
日本では注目されているIoTによる現場の可視化と、それによるボトルネックの把握、そして生産性改善というテーマについても「Improve Productivity」という大きく書かれた展示が目立っていた。
この辺は中小工場を多く抱えるドイツでも同じテーマ性があると言えるのだろう。
画像解析を活用した品質検査や音声認識エンジンを活用した指示、ロボットとの協働など、様々なテクノロジーが多くのブースで紹介されていた。
インダストリー4.0はどうなったか
インダストリー4.0という言葉について、当初この言葉を概念的に正しく捉えている人はとても少なかった。
昨年くらいから共通認識が出来上がり、インダストリー4.0とIndustrial Internet Consortium、日本からはIVIがそれぞれのアーキテクチャモデルを持ち寄りすり合わせを始めていることもあってか、説明員の方々の解説にはよく「Digital Twin(デジタルツイン)」という言葉が登場した。
ただ、生産のプロセス(時にはサプライチェーンも巻き込んで語られるプロセス)全体におけるデジタルツインの話題を語る企業と、一つの産業機械の状態をデジタルデータとして取り出すことをデジタルツインと呼ぶ企業とが並存している状態であった。
そもそも、インダストリー4.0では、製造すべき製品を設計し、工場の生産ラインもデジタル上で表現し、製造をシミュレート、継続的に改善するという大きな流れがあるので、後者は「狭義のデジタルツイン」とも呼べるのかもしれない。
言葉の定義はそこそこにして、具体的な展示を見ていくと、可視化をテーマとする展示が多い中、可視化の先を見据えた展示もそれなりに見受けられた。
一つは上位のビジネスプロセスとの統合だ。SAPなどビジネスシステムを提供する企業はもちろんのこと、シーメンスやダッソーなど製造業を支援するような情報システム、IoTプラットフォームを提供する企業でも、上位のビジネスシステムとの接続性を担保するような概念モデルを提示し、MindSphereはすでに多くの企業が自社向けアプリケーションを開発し、ビジネスシステムとして活用が始まっていることがわかった。
プラットフォーム化と産業別テーマ化の現状
後日、シーメンスのブース解説で詳解するが、今回注目した展示として、IoTプラットフォームとしてのMindSphereの展示が具体的になってきていたということがある。
これまでSAP上でしか提供されてこなかったMindSphereだが、既報の通りAWS上で提供されるようになり、年内にはAzure上でも提供される予定だという。
実際、プラットフォームとしては、多様なデータを収集し蓄積しやすいということ、自社の可視化ツールだけでなく、多くの分析ツールが利用可能であるということ、そして、集めたデータを活用して自分たちでもアプリケーション開発を行うことができて、さらに、マーケットプレースで販売することができるというところまで完成していて、具体的な展示も行われていた。
また、多額の資金を投じてシーメンスが持つ産業別のノウハウもMindSphere上でアプリケーション化を進めていることも確認できた。
今後の産業向けIoTプラットフォーム(クラウド側)におけるデファクトスタンダードを目指す準備が整ってきたのだといえるだろう。
今回、様々なブースを取材した内容を書いてきたが、これまで言われてきたスマートファクトリーの概念モデルは、大枠ではあるがかなりのレベルで実現可能なソリューションが揃ってきたという印象を受けた。
今後、日本のすり合わせ、部分最適文化が、大枠の概念モデルを埋めるようなソリューションを生み出す余地は大きいと思われる。生産性改善だけでなく、製造における様々なテーマを解決する製品やサービスの登場に注目は移っていきそうだ。