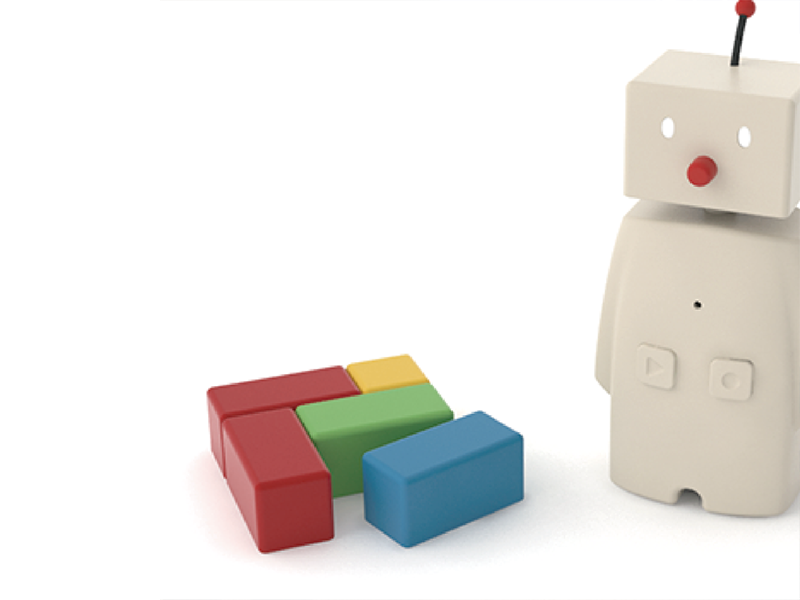今、ロボットがアツい。個人レベルの人から、大企業まで様々なロボットを作っている。
その中でも、ソフトバンクがプロデュースするPepperはとても有名だが、何ができるのか?誰でも動かせるのか?そういったことまで知っている人は案外いない。
実際は、アルデバラン社が提供する開発キットをダウンロードしてきて、簡単な操作でプログラムできるようになっている。
ペッパーには、あらかじめ相当な数の動きが登録されているから、登録されている動きをつなげていけばできると考えてもらえればイメージもつきやすいだろう。
先日、個人でPepperを購入したというツワモノ(?)とお話する機会があったのだが、一般家庭に置くと、家庭内に亀裂が入るくらいデカイ(笑)とおっしゃっていた。
普段イベント会場などに配置されているのを見かけるからサイズ感があまり気にならなかったが、感覚としては、冷蔵庫が二つある感じで、実際に家に置かれている写真を見せていただいたのだが確かに大きい。
いくら高性能といえども一般の家庭に置くのは現実的ではなさそうだ。
一方、小型のロボットを作ってる人もいて、ユカイ工学の家庭をつなぐコミュニケーションロボット「BOCCO」とか、ディアゴスティーニから全70号のパーツ組み立てロボット「ロビ」、自分でプログラムできるロボット「RAPIRO」など、様々なものが手に入る。
見ての通り、これらのロボットは、顔がある。
人型にするのはなにもアニメの影響からではなく、無機質なものに向かって声をかけたりするのは抵抗があるので、顔があることで親しみがわくからだ。
以前、ソニーがAIBOという犬のロボットを作って話題になったことがあるが、動物というアプローチもある。
家に置くことを前提としたロボットを作る場合、もちろん何ができるか?ということも重要だが、どういうデザインであれば家に置きたいか、もっと言えば、おもちゃではなくインテリアとして成立するか、そういったことを考慮したロボットのデザインが今後重要となっていく。