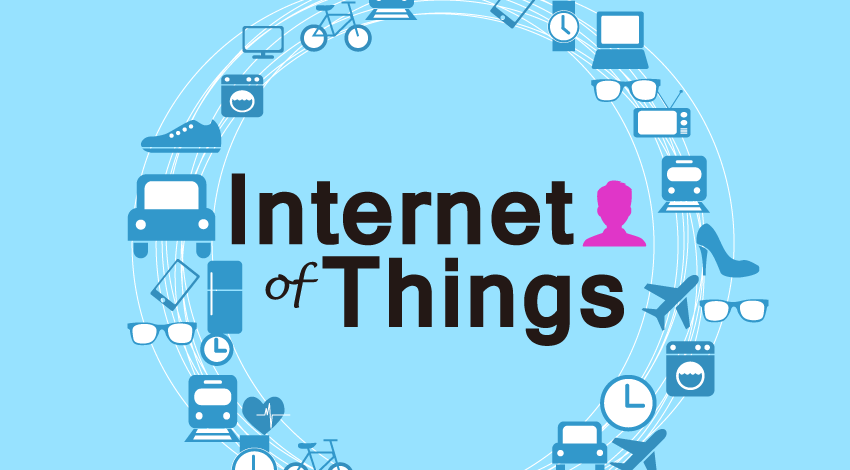IoTをゼロベースで考えるの第13回目は、いまさらだが、IoTとは何なのか?について書く。
というのも、ここ最近で、IoTという言葉が溢れている。機運が盛り上がってきたのはうれしい限りだが、一部の人以外には「なんのこっちゃわからん、説明してくれ!」とよく言われている状態だからだ。
IoTにおける情報の流れ
IoTについて書かれたニュース記事などを見ると、よくセンサーとか、クラウドとか、AIとか、いろんなキーワードが出てくる。
IoTとひとくくりにされているにもかかわらず、一見関係なさそうなそれぞれのコトを並べられると、よくわからないという状態になるのが常だ。
まずは、IoTと呼ばれるものを概念的に考えるまえに、IoTにおける情報の流れを整理する。
まず、モノのインターネットと呼ばれるIoTだが、「モノ」と呼ばれる部分は、図でいう「センサー類」、「挙動」と書かれるボックスのことだ。
センサーというのは、温度センサーでも、人感センサーでも、なんでもよい。カメラなんかでもよいのだ。さらに、挙動というのも、スマートフォンになにかが表示されるのでもいいし、モーターでロボットのようなモノが動くのでもよい。
このなんでもよさが、まずわかりづらくしているのだが、一旦そういうものだと思ってほしい。
これまではモノはインターネットにつながっていなかった
これまでは、モノはインターネットにつながっていなかったから、「センサー」で検知した情報はそのまま「挙動」に変わる。例えば、冷房の温度設定がある一定の温度帯を超えると、冷やし始めたり、冷やすのをやめたりするといったものだ。
この「挙動」の部分が「センサー」部分の測定した結果に基づいて、インターネットを経由して変化すると考えるとわかりやすい。
家の冷房がインターネットを経由して温度を変えると何がいいのだろう?
家の温度をセンサーで取り続ける際に、外気温もセンサー(というか温度計)で計測するとする。
つまり、外気温と室温を計測し続けるのだ。
冷房が動いている間、毎日、毎日、外気温と室温の差を知ると、統計的にこの家にいる人が、「外気温が何℃だろうと、25℃が好き」なのか、「外気温-3℃くらいが好き」なのかがわかる。
これまでの冷房は、「外気温が何℃だろうと、25℃が好き」というニーズにはこたえられた。もしかしたら、「外気温-3℃くらいが好き」という設定ができる冷房もあるのかもしれない。
しかし、情報を一旦クラウド上のデータベースに蓄積(②)し、分析(③)することで「常に外気温の-3℃くらいに保て!」という挙動を「自律的に」作ることができるようになるのだ。
あたかも、個人の好みを冷房がわかっているように。
これだけだと、大したありがたみはないと思う人がいるかもしれない。手動で温度を変えても大した手間ではないからだ。
しかし、昨今の空調は常時つけておいたほうが省エネだということがある。
では、常時つけておくのに適切な温度は何℃だろう?家にいないことは冷房は勝手に認識してくれるのだろうか?ということまで考えると、もう一つの最近家によくある人感センサーもインターネットにつながると活躍するかもしれない。家の各所に配置された人感センサーが留守を認識すると、「冷房は家が温まりすぎないように注意しながら、無駄な電力を使わず適度に冷やす」のだ。
省エネというのは、なにも電気を切りまくればよいというわけではなく、いかに効率的に全体として無駄な電力をつかなわいようにするのか?が重要だが、この例であればセンサー類がインターネットにつながることで、なるべく無駄な電力を使わなくても済むことがわかるだろう。
このように、IoTというのは製品のグループや何かを表す言葉ではない。これまでのように、IoT製品 世の中にある、多くのモノがインターネットにつながることで、ヒトに対してなんらかの価値を生み出すのだ。
では、何がIoTなのか?
先の例でいうと、センサーが検知した情報を、インターネットを経由してクラウドに蓄積し、分析して、モノの挙動に返さないとIoTとは呼ばないこととなる。
そうすると、例えば、
- 空を飛んでいるだけのドローンはIoTではないのではないか?
- Pepperは自立して動いているからIoTではないのではないか?
- AIは人工知能のことでIoTとは関係ないのではないか?
という疑問がわいてくる。
しかし、IoTNEWSでもこれらのモノをIoTとしてとらえている。
これは、なぜかというと、自律して動くことができるモノも、今後はインターネットとつながるようになり、さらなる価値を生み出すという方向に向かっているからだ。
例えば、ドローンでいえば、コマツの事例のように、ドローンで測量(①)した地面のデータをクラウドにあげ(②)、分析(③)することで、建設機械を効率的に動かす指示をだし(④)工期の短縮に貢献している。
つまり、IoTを語るとき、IoTの流れで示した一部分を担うモノと、この流れ全体を実現できているモノがあって全体のモノだけをIoTと呼べば混乱はないのかもしれないが、実際は洗濯機や、冷蔵庫というように、「IoTという製品分類」があるわけではないことを理解する必要があるのだ。
この概念を理解してIoTを見ると、例えば、AIであれば「ああ、③分析のところのことを言っているのだな」、ドローンであれば「①センサー(この場合画像を収集するカメラ)のことを言っているのだな」とわかるだろう。
実際想定されているIoTの作る社会は、これほど単純ではなく、センサーもたくさんあり、挙動もたくさんあるという状態で実現されるので、かなり複雑ではあるが、簡単な例から慣れていけば決してイメージがわかないものではない。