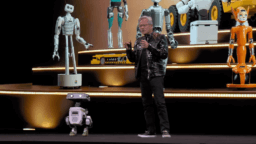今回のCES2020レポートはクルマの分野から。
クルマ産業がCESに展示を開始してから久しいが、今年の傾向としては、まず数年前によく展示されていた、自動運転を支える技術についてはほとんど展示がなくなったことだ。
NVIDAを中心として、クルマがいかに周囲の物体を認識し、自動的に運転を行うか、ということについては、多くの企業が実証実験フェーズに入り、それを珍しいとは思わなくなったからだろう。
また、以前は自動運転の世界ではコックピット周りがどうなるのか、という展示もたくさんあったが、こちらも一息ついたようだ。
コンセプトを打ち出すことはできても、実際に自動運転のクルマが走る社会は当面やってこないので、これを続けていても仕方ないともいえる。
その結果、未来のコンセプトカーのモックアップが再び展示されるようになったり、実際に販売されるクルマが展示されるようになり、映像で未来が語られるようになるわけだが、既視感もあり、驚くことはできない。





一方で、今回話題となっていたのは、センシング技術など既存のクルマ産業が使える技術だ。
例えば、ボッシュが提案する目の部分だけを陰にするサンバイザーや、ソニーがVISION-Sというクルマで利用する各種センサー技術の展示がこれに当たる。
ソニーが完成車両を展示したということで、驚きもあったが、実際にVISION-Sで使われている33個のセンサーは未来のセンサーというわけではない。ソニーは、スマートフォンにおいてXperiaを生産していて培った部品ノウハウを様々なメーカーに提供しているわけだが、今後のクルマ産業のゲームチェンジにおいて、スマートフォンと同じく要素技術を提供していくには今回のようにクルマを見せるのが理解されやすいという視点なのだろう。


エンターテイメントの分野でも、車内のどこにいてもよい音質で音楽を聴くことができるという360°オーディオが話題となっていたが、これはオーディオコーナーで展示されていた。

様々な基礎技術を研究しているソニーだからこそ、技術をどのようにプロダクトに実装するのかを分かりやすく提示することが重要なのかもしれない。
今回のCESのテーマである「体験」という視点からいうと、BMWがi3の助手席をリラクゼーション空間に変える展示を行っていたのが印象的だった。


この車は、アーバンスイートと名付けられていて、室内ではリラックスするシート、照明、スマートフォンや映像コンテンツを楽しむための装置がつけられていて、移動をどう楽しむのか、という具体的な提案になっていると感じた。

屋内展示においても、室内空間でどうリラックスするのかという展示が行われていて、上の写真のシートを実際に体験すると、シート全体がリクライニングし、ゆったり音楽を聴くことができるようなシートも提案されていた。
無料メルマガ会員に登録しませんか?

IoTNEWS代表
1973年生まれ。株式会社アールジーン代表取締役。
フジテレビ Live News α コメンテーター。J-WAVE TOKYO MORNING RADIO 記事解説。など。
大阪大学でニューロコンピューティングを学び、アクセンチュアなどのグローバルコンサルティングファームより現職。
著書に、「2時間でわかる図解IoTビジネス入門(あさ出版)」「顧客ともっとつながる(日経BP)」、YouTubeチャンネルに「小泉耕二の未来大学」がある。