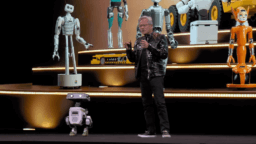ボッシュはドイツのレニンゲン研究センターの完成を機に、学際的なコラボレーションを奨励し、同社の革新力をさらに強化したいと考えている。
シュトゥットガルト郊外に完成した新しい研究開発・先端エンジニアリングセンターでは、独創力豊かな約1,700人の従業員が応用産業技術研究に従事している。
ドイツ連邦共和国のアンゲラ・メルケル首相やバーデン・ヴュルテンベルク州のヴィンフリート・クレッチュマン州首相をはじめ、政財界、学術界から数多くの賓客を迎えて開所式が執り行われ、新しい研究センターが正式にオープンした。
「大学がそうであるように、私たちの研究センターには数多くの学際チームが揃っています。私たちはここで働く研究者たちに、未来に実現できる可能性を考えるだけでなく、それ以上のことを成し遂げてほしいと考えています。それは、企業家としての能力を磨くことです。レニンゲンはボッシュ版のスタンフォードともいうべき存在で、同時に新センターは工業立国としてのドイツの未来を信じる私たちの思いが込められた場でもあります」と、ボッシュ取締役会会長のフォルクマル・デナーは挨拶の辞を述べた。
ボッシュ・グループは、この新しい拠点の建設に3億1,000万ユーロを投入している。
『何百万ものアイデアのネットワーク化』をモットーとして掲げる新研究センターは今後、ボッシュのグローバルな研究開発ネットワークの中核として機能する予定。
また、ボッシュはここで従業員の起業家精神を育てたいと考えている。
デナーは、ドイツが抱える競争上の弱点がまさにここにあると見ている。「ドイツ国内では、起業の機会だけでなく、意欲もあまり見かけません。そのため、特に若手の大卒者の企業家精神を養う必要があると考えています。この点において、大学には高度に専門的な試験に合格するための知識を教授するだけでなく、より多面的な教育の実施を望みたいと思います」

人々の生活の質の向上に役立つ技術革新
レニンゲンでは、人々の生活の質の向上に役立つ革新的技術を数多く生み出すことが期待されている。
この研究センターには、電気工学、機械工学、コンピューター科学、分析、化学、物理学、生物学、マイクロシステム技術など、さまざまな分野の科学技術研究者が集まっており、本社の研究開発・先端エンジニアリング部門に属する約1,200人の従業員、そして博士課程の学生とインターンあわせて500人がここで未来の技術的課題に挑んでいる。
これらの研究者たちはこれまで、シュトゥットガルトエリア内の3カ所の拠点に分散していた。
幅広い技術分野を扱う研究開発・先端エンジニアリングセンター
独特の雰囲気に包まれた環境の中で、パイオニア精神豊かなボッシュの従業員が新製品と革新的な生産手法の両面で研究活動を行っている。
その主要なテーマは、ソフトウェア工学、センサー技術、自動化、ドライバー アシスタンス システム、バッテリー技術、自動車用の改良型パワートレインシステムなど。
なかでもこのところ特に重視されるようになったのが、ソフトウェア工学、とりわけIoTに関連したネットワーク化のためのソフトウェアだ。
ボッシュ自体については、来るネットワーク化時代への備えが十分にできているとデナーは考えている。
たとえば、ボッシュ・グループはマイクロメカニカルセンサー市場のグローバルリーダーであり、ソフトウェア分野でも数年前から専門知識の蓄積が進んでいる。
ボッシュ・グループは現在、1万5,000人を超えるソフトウェアエンジニアを擁しており、IoT分野だけで約3,000人のエキスパートが活動している。ボッシュは特に、ネットワーク化がもたらすサービス分野の遠大なビジネスチャンスに注目している。
ドイツが勇気を学ぶべき時
デナーは、ボッシュのような大企業では、企業と起業家精神が栄えるようなスペースを用意する必要があるとも述べている。ボッシュは率先して、そうした仕組みの整備に取り組んでいる。
その1つは、新しいビジネス分野に参入するためのスタートアッププラットフォームの構築だ。
デナーは、シリコンバレーが欧州にとって進むべき道を示す真のモデルであるならば、「私たちはリスクを取ることを学ぶ必要がある」と述べている。
そこで、ボッシュの研究者たちが実業家として成功できるよう支援するためにBosch Start-up GmbHを立ち上げ、施設の維持運営や財務、その他の事務管理業務などを担わせることにした。これにより、新しい事業部は最初から製品開発とその市場導入に全精力を集中できる。
そうした道筋を経て開発された最初の製品の1つが、農作業ロボットの「Bonirob」だ。育種と農場管理に当たるコンパクトカー並みサイズのこのロボットは、ボッシュ傘下の新興企業であるDeepfield Roboticsが開発した。
独創的なアイデアを生む最適な作業環境
広大な研究センターには、農作業ロボットをテストするスペースが十分に確保されている。
構内には本館と、11の実験室棟、作業用建物のほか、サイト管理用のユーティリティー施設が2棟あり、さらにドライバー アシスタンス システムを試験するための近代的なテストコースもある。
どの部門がどのビルに入居するかは、ネットワークマトリクスを使って決められた。その基本となったのは、個々の学際分野間の情報交換の緊密度だ。新しい研究センターでは、関係が密な部門ほど、相互間の物理的距離が短くなるよう建物が配置されている。

閑静なコーナーとコラボレーションゾーン
ボッシュはレニンゲンの作業条件に格別の注意を払っている。建物の内外とも、研究者にとっての作業環境は非常に近代的で、基本的に施設全体がひとつの職場を形成している。
「新鮮な空気の中でのインスピレーションの交流、水辺で生まれる技術 – ここレニンゲンではそのすべてを実現できます」とデナーは述べている。
建物内、敷地内のあらゆる場所でWi-Fiに接続できるようになっており、ノートPC、タブレット端末、そしてボイスオーバーIPを利用し、施設内のどこにいても作業を進めることができる。
その基本となった構想について、デナーは次のように語った。「レニンゲンでは、イノベーションを生み出すチームのために閑静なコーナーとコラボレーションゾーンを用意しました」。
また、オフィスのレイアウトはイノベーションプロセスの総合的な解析をもとに設計された。
アイデアを練る時に、研究者は邪魔の入らない閑静な環境を必要とする。
さらに重要なのは、その後の同僚との意見交換と「コラボレーション」だ。センターのプランニングにあたり、そうした流れと従業員の希望も考慮された。

関係者全員による合同協議の結果、全く新しいオフィスコンセプトが生まれた。
レニンゲンの研究施設の建物には、個々の作業スペースのほか、大小さまざまな会議室が270室ほど設けられている。一人で集中したり、チームで作業するスペースが十分に用意されており、これがこのセンターの大きな特徴となっている。
また、各従業員の席から最寄りの会議室までの距離は平均10mほどで、次の革新的な突破口までの道のりも同じくらいの距離であってほしいと考えている。

【関連リンク】
・ボッシュ
無料メルマガ会員に登録しませんか?

IoTに関する様々な情報を取材し、皆様にお届けいたします。