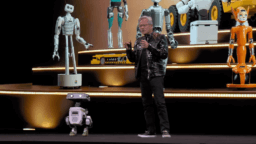3. スマホユーザーの実態にみる、顧客ニーズの変化
これまで見てきたように、イノベーションによって顧客ニーズはますます多様化していく。しかし注意すべきは、顧客は必ずしも”目新しい製品”を求めているわけではないということだ。顧客が本当に欲しいモノは何なのか、こまかく分析していく必要がある。
その一例として、いまや生活者の”身体の一部”とも言える、スマートフォン(以下、スマホ)の実態について紹介したい。
株式会社電通が進めている「電通モバイルプロジェクト」では、2003年から2か月に1度、モバイルユーザーの利用状況を調査し、その実態を追い続けている。
そのリーダーを務める吉田健太郎氏によると、スマホユーザーの最近のトレンドは「アプリの断捨離」だという。
つまり、世の中には膨大な数のアプリが存在するものの、ユーザーは、自分が頻繁に使うアプリだけを残し、それ以外は削除する傾向にあるということだ。
また、吉田氏のレポートによると、ユーザーが日々使うアプリの種類は、時が経っても変わらないという。3年前にスマホで音楽を聴いていた人は、今も聴いている。逆に、3年前にスマホで音楽を聴いていなかった人は、今も聴いていない可能性が高いということだ。
理由は、ユーザーは限られたリソースの中で自分がしたいことだけをするためだという。バッテリーの「容量」も、スマホを使って楽しめる「時間」も有限だ。その有限な環境の中で、自分が本当にしたいことができる環境を顧客は求めているというのだ。
また、中国のIT企業テンセントが展開するWechatは、本来はコミュニケーション・プラットフォームだが、今では電子決済のしくみも併せて、中国の社会インフラのように国民に浸透している。
そこからは、用途ごとにアプリを保有したりサービスの登録をしたりするのではなく、共通化されたプラットフォームの上で、最低限の目的を兼ねたいという消費者の傾向が見て取れる。
こうした実態からは、顧客は必ずしもさまざまな種類の製品を求めたり、世界で自分しか持っていない製品を求めたりする傾向にあるわけではなさそうだ。
むしろ、選択肢が増えすぎた世の中においては、消費者のニーズは均質化する傾向に回帰しているとも言える。
スマホの例でさらに付け加えると、日本国内のiPhoneのシェアは2018年1月時点で45.9%だという。つまり、国民の半数がたった一つの企業の製品を利用しているのだ。
この理由について電通の吉田氏は、「日本人は周囲と同じものを好む傾向にある」と分析している。同じものを好む日本人の特性は昔も同じだ。
ニーズが多様化する時代には、普遍的な国民性などを考慮することも重要だと言える。
次ページ:インダストリー4.0時代、メーカーに必要な3つのポイント
無料メルマガ会員に登録しませんか?

技術・科学系ライター。修士(応用化学)。石油メーカー勤務を経て、2017年よりライターとして活動。科学雑誌などにも寄稿している。