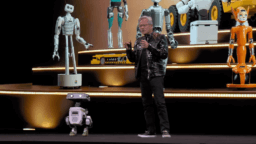経営層がゴールを設定すべき
鍋野: 未来の計画や方針について、IoTのプロジェクトを現場で担当している人たちに考えろと言うのはかわいそうな話です。会社がどこに進むべきなのか、あらゆる業務のどこを最適化するべきなのか、全体を俯瞰している人じゃないと判断できません。そこは本来、経営責任のあるマネジメントの人たちが考えるべきです。そのことに、日本も最近ようやく気がつき始めたという感じがします。
小泉: そうすると問題は、経営者がいかにゴールを設定するかという話になると思いますが、私も色々な人にお話を聞いてきて感じることは、日本人はゴールを置くのは苦手なんだなということです。
八子: そうです、結局そうなんです。「わからない」ことを理由に、「俺が決めたんじゃない」と言いたいのです。ですから、さきほども言ったように、わからないのだったら、「技術的なロードマップはこうなるのだから、こうしませんか」という話を私は企業の方にしてきています。
「そんなことまでやらないといけないのか」と言う人もいます。やらないならそれでかまいません。ただ、私はこの話を他の人にも言っているわけですから、あなたがやらないのなら、他の人がやります。結局、やる人はやりますが、やらない人はやらない。
鍋野: そうですね。大事なことは、マネジメントの「やる/やらない」の判断です。便利なツールはそろってきているわけですから、そのツールを今までの感覚で使うのではなく、「ここに到達したいから使う」、「到達するためにもっといい道具が探せばあるのではないか」という観点を持ってほしいですね。

小泉: なるほど、「デジタル」というと難しい話のように思われがちですが、もはや身近なものですからね。スマートフォンがわかりやすい例です。
ERPにおいては、データが高速で上がってきてたくさん処理できるようになったら、自分だったら何できるかというイマジネーションを経営者の方には持ってほしいですね。本日はありがとうございました。
無料メルマガ会員に登録しませんか?

技術・科学系ライター。修士(応用化学)。石油メーカー勤務を経て、2017年よりライターとして活動。科学雑誌などにも寄稿している。