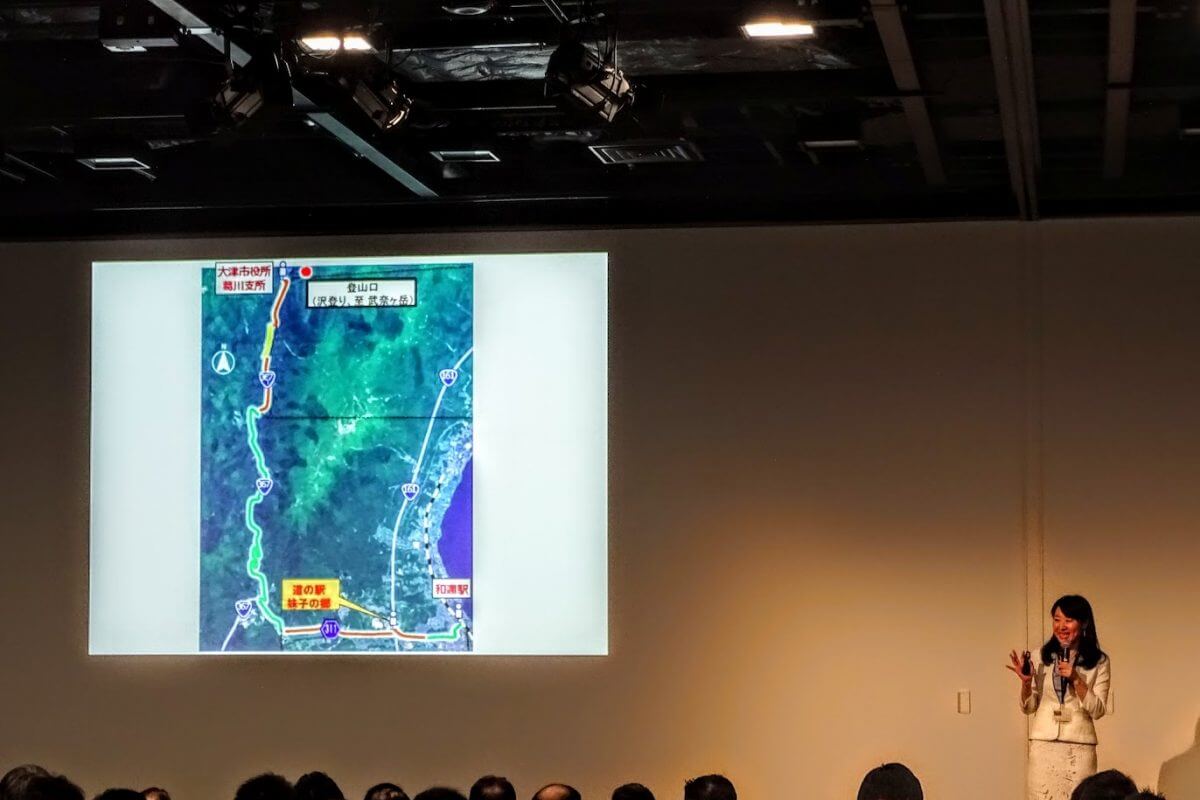地方の過疎化・高齢化が進む現在、解決すべき重要課題が交通だ。
バスなどの公共交通機関は地方の高齢者にとって大事な移動手段だが、人手不足による路線廃止などの問題を抱える自治体もあるという。そして交通手段の不足は、経済振興を止めることにもつながってしまう。
一方で、高齢者が自力で運転するにしても、今年の春より60代以上のドライバーによる事故の多発に見られるように、高齢者の運転が引き起こす自動車事故が社会的な問題になっている。
こうした地方交通の問題を解消するために、経済産業省・国土交通省が2019年4月より「スマートモビリティチャレンジ」を開始し、同年6月21日に東京ミッドタウン日比谷にてキックオフシンポジウムを開催した。
この「スマートモビリティチャレンジ シンポジウム」では、経産省・国土交通省の支援を受けて新たなモビリティーサービスに取り組む5つの自治体が講演を行った。
今回は各自治体がそれぞれ抱える固有の交通課題に着目しながら、「スマートモビリティチャレンジ シンポジウム」における講演をレポートする。
「スマートモビリティチャレンジ」とは
まず「スマートモビリティチャレンジ」だが、これは新しいモビリティーサービスの社会実装に挑戦し、地方の移動課題および地域活性化に挑戦する地域や企業に対し、経済産業省と国土交通省が支援を行うという取り組みだ。
今回登壇する地方自治体は、事業計画策定や効果分析などに協力してもらうために経産省が選定した「パイロット地域」(13地域)か、全国のけん引役となる先駆的な取り組みを行うために国土交通省が選定した「先行モデル事業」(19事業)のいずれかに該当する自治体である。

冒頭で登壇した経済産業省・参事官の小林大和氏は、「『スマートモビリティチャレンジ』は移動のみを単体で捉えて事業を進めるのではなく、観光や物流といった多様な経済活動と連携し、潜在需要を掘り起こし、地域全体を活性化するという、モビリティと非モビリティを掛け合わせたMaaS(=モビリティ・アズ・ア・サービス)が重要だ」と述べた。
小林氏によると、この取り組みは今年春から第1弾のトライアルを開始し、各自治体との課題整理とフィードバックを繰り返しながら、2022年以降には各自治体のサービスが全国に拡大できるように勧める予定とのことだ。
次ページは、「高齢化問題に対応する自動バス運転実証実験」
無料メルマガ会員に登録しませんか?

1986年千葉県生まれ。出版関連会社勤務の後、フリーランスのライターを経て「IoTNEWS」編集部所属。現在、デジタルをビジネスに取り込むことで生まれる価値について研究中。IoTに関する様々な情報を取材し、皆様にお届けいたします。