人口減少やテクノロジーの進展によって、私たちの「まち(街・町)」はこれから大きく変わることが必至だ。しかし変わるといっても、「どこ」へ向かえばいいのだろう。道筋を鮮明にイメージできている人は、どれだけいるだろうか。
そのヒントを与えてくれる人物がいる。東急電鉄の執行役員である東浦亮典(とううら・りょうすけ)氏である。東浦氏は昨年、初の著書『私鉄3.0 – 沿線人気NO.1・東急電鉄の戦略的ブランディング-』を上梓した。
帯に書かれているのは、「電車に乗らなくても儲かる未来、それが私鉄3.0!」という言葉だ。現役の執行役員という立場で、東急電鉄の歴史をひも解きながら未来のビジネス構想まで語ったこの著書は、業界内外で大きな反響を呼んだ。
日本の多くのまちは鉄道の駅を中心に栄えてきた。これまで、私鉄企業として鉄道を敷設するだけでなく、その沿線のまちづくりにもコミットすることで発展してきた東急電鉄を、東浦氏は「まちづくりデベロッパー」と定義する。今年、鉄道部門を分社化することも決まっている東急電鉄は、未来のまちづくりを見据えた戦略をこれまで以上に推し進めようとしている。
本稿では、東急電鉄が目指すビジョンや、私鉄企業という視点から東浦氏が見据える日本の未来のまちのあるべき姿について、話をうかがった(聞き手:IoTNEWS代表 小泉耕二)。
東急のビジョンは2.0モデル、3.0はその先に
IoTNEWS 小泉耕二(以下、小泉): 『私鉄3.0』を書かれた背景について教えてください。
東急電鉄 東浦亮典氏(以下、東浦): 実は、渋沢栄一氏が創設に関わった当社の前身となる「田園都市株式会社」の設立から数えて、昨年がちょうど100周年でした。その機会に当社の開発の歴史とビジネスモデルを再整理しておきたいと考えて筆を執りました。
昨年発表した当社の中期経営計画(2018年度~2020年度)は、2.0までのモデルを示したものだと考えています。その前の1.0モデルは、いわば20世紀の東急電鉄のモデルです。郊外に宅地を販売して、そこに居住してきたお客様に毎日電車で通勤してもらい、ターミナル駅に商業施設などを設けてお買い物を楽しんでもらう、というビジネスモデルです。
しかし、人口減少や働き方の多様化に伴い、そうした「通勤」をベースとしたビジネスモデルは立ち行かなくなります。そこで新たに策定したのが2.0モデルです(後述)。東急は今、2.0のモデルにようやく足がかかってきた状況だと、私は考えています。
そして、私が『私鉄3.0』で述べた3.0モデルは、中期経営計画のさらに先のビジョンであり、まだ東急電鉄では議論されていない、私の個人的な考え方です。ですから、個人として本に書いたのです。
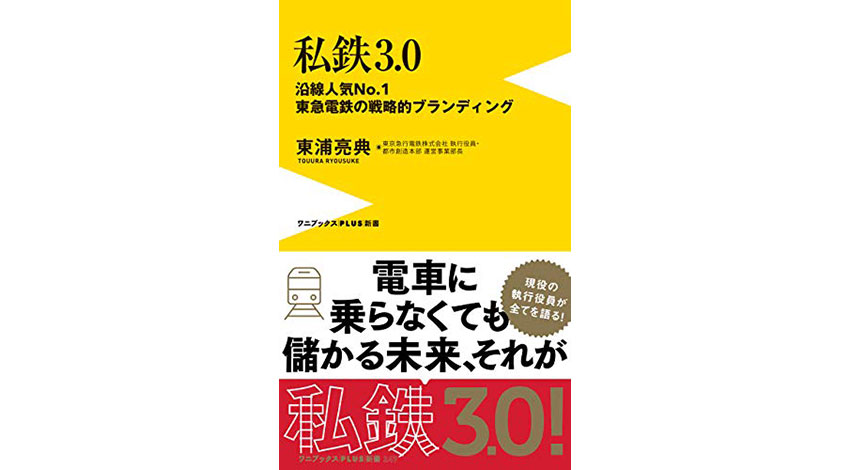
小泉: 東急電鉄がかかげる2.0モデルと、その先に続く3.0モデルとは、どういうものでしょうか。
東浦: 東急電鉄は従来から、観光路線を持たない鉄道会社です。他の私鉄各社は、基本的には都心から観光地まで人を運ぶ観光路線をもちます。東武線は日光、京浜急行は三浦海岸、小田急は箱根というように。
ですから、実は東急電鉄の本質は、鉄道事業そのものよりも、そもそも沿線のまちづくりにあったのです。私が東急電鉄を「まちづくりデベロッパー」と呼ぶのは、それが理由です。
小泉: 東急電鉄は今年、鉄道事業部門を分社化しますね(※)。このことは、「まちづくりデベロッパー」としての取り組みとどう関係してくるのでしょうか。
※東京急行電鉄は今年の9月2日に「東急株式会社」に社名を変更する。なお、分割した鉄道事業を承継する子会社は「東急電鉄分割準備株式会社」として4月25日に設立済であり、同じ9月2日に「東急電鉄株式会社」に社名を変更する予定だ。
東浦: 最新の予測によれば、東急沿線は幸い2035年まで人口減少に転じません。しかし、いずれ必ずきます。すると当然、鉄道事業は自らの努力だけでは需要は喚起できません。都市開発や都市型観光と一体となって需要喚起を進めていかなければなりません。
そこで、鉄道部門は分社化して安全投資に対して意思決定を迅速にし、お客様に近いところでビジネスを行い、東急は都市部門や生活部門を柱とするようなビジネスモデルに注力しようと考えたのです。
無料メルマガ会員に登録しませんか?

技術・科学系ライター。修士(応用化学)。石油メーカー勤務を経て、2017年よりライターとして活動。科学雑誌などにも寄稿している。




















