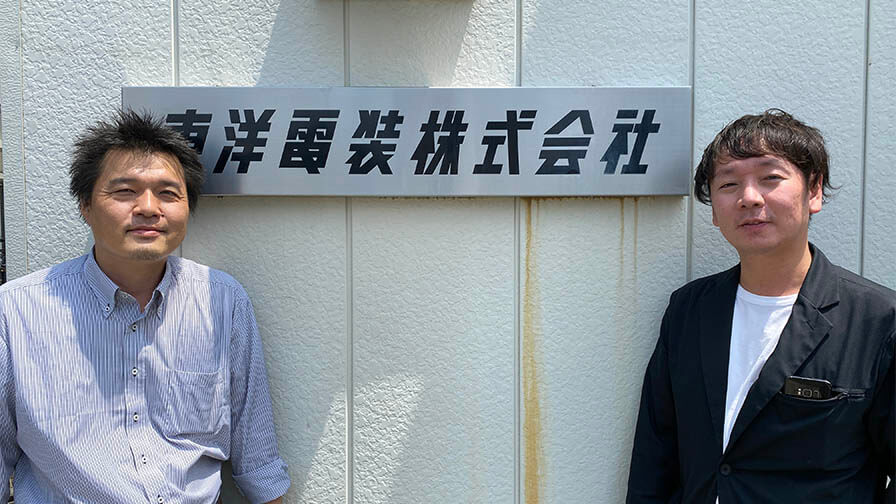昭和48年に広島でビルの空調や、官公庁などのダムや水道局、発電所や工場などの施設に配電盤・制御盤を納めるメーカーとして創業した東洋電装は、その後工場の制御を行う制御機器や、衛星通信の基盤、最近では介護領域のソリューションを提供する企業だ。
なかでも、高速道路において非常時に必要となるIPノードを一体型にした非常電話を手がけたことをきっかけに、有線・無線での様々な通信サービスの設置を手掛けることになる。
その後、カメラ画像からサービスエリアの満空状況をAIで認識するシステムや、遠隔による鍵管理システムによる省人化や管理・監視を行うソリューションなど、さまざまなソリューションを提供している。
制御技術と通信技術の上に載せられた、クラウドやAIのソリューション。そうしたDX領域での活動を行うため、「TDX」と呼ばれるDX専門部隊が設立されたということで、東洋電装 執行役員 制御盤事業 事業マネージャー驛場 啓之氏と、IoTシステム開発事業 プロジェクトマネージャー岡田 祐介氏、広報担当 小田 紀子氏にお話を伺った。
(聞き手:IoTNEWS代表 小泉耕二)
きっかけは製造現場の「困りごと」解決
IoTNEWS 小泉耕二(以下、小泉): TDXはいつ発足されたのでしょうか。
東洋電装 岡田祐介氏(以下、岡田): 「TDX」という言葉が生まれたのは2年前です。これは、東洋電装の「TD」と、「DX」を重ねた造語で、その時に掲げた目標が「業務の効率化とコスト削減」といった、工場で使われるソリューションを産むことです。
小泉: 現在TDXで行われている具体的なサービスについて教えてください。
アンケート端末「CSモニタ」を活用したアンケート収集サービス、人の在室・不在の情報を表示する「出退表示システム」、LPWAを活用した無線機の開発、RFIDを活用したソフトウェア開発、工場設備のデータ収集・分析、設計から納品まで行う受託開発などを主に行っています。

小泉: もともと制御盤開発からスタートされ、高速道路開発、通信事業に参入し、TDXではソフトウェア開発も行われているのですね。
現在ではトータル・サポートを行える環境を構築されていますが、TDXを始めるきっかけはなんだったのでしょうか。
岡田: きっかけは、もともと私が製造業の現場にいたということもあり、現場の困りごとを理解していたことです。
現場で使われる、IoTのソリューションはパッケージ売りが多く、現場に合わず活用できないケースが多くありました。そこで東洋電装の技術を活かし、現場の「困りごと」を解決するものを作るために発足されたという経緯があります。
小泉: 現場に合わせてソリューションを提案されているのですね。具体的にはどのように進めていくのでしょうか。
岡田: 要望を聞き、可能であれば現場まで伺いヒアリングを行います。解決したい課題や実現したい内容に対してディスカッションを行いながら、作り込んでいきます。
東洋電装 驛場啓之氏(以下、驛場): また、オリジナルの機材を開発した方がいいのか、汎用品で賄えるか、そうしたことから検討や提案を行っています。汎用品で解決できるのであれば安価に納めることができるというメリットがある一方で、要望にマッチしない場合もあるので、「要望に対してベストな形が何なのか」を徹底追求しています。
オリジナルの機材を開発する場合は、自社やパートナーと開発を進め、ニーズに応えていきます。
様々な視点から顧客に寄り添う
小泉: ひとつひとつのサービスにこれまでの経験が活きているのですね。受託開発を行っている企業は他にもあると思いますが、御社の強みは何だと思いますか。
驛場: モノづくり、通信、技術開発と、自社で一貫して行えるという点は強みだと思います。
検証を進める段階でも、現場や技術者など、様々な角度からの観点でブラッシュアップしていくことができます。
そして実際に試作を作って改善していく段階でも、寄り添いながらもスピード感を持って進めることができます。
小泉: TDX単体で動いているというよりは、会社全体で案件を進めているのですね。東洋電装、TDX、子会社含めた全体で、実際に過去どういうものを作ってこられたのでしょうか。
東洋電装 小田紀子氏(以下、小田): もともとインフラに使われる制御盤を作っていたのですが、その後高速道路の通信設備で使うIPノードと一体化した非常電話をつくりました。もともとただの電話だったわけですが、そこに通信機能をいれていくことで、遠隔操作や遠隔監視、映像伝送などができるようになりました。
利用者から見ると一般的な電話ですが、様々な装置が入っており、現在、西日本高速道路でのシェア率70%以上です。

この高速道路の案件で、長距離無線LANを構築したのですが、基地局タイプや可搬タイプ、車載タイプと様々な機材を開発しています。
開発を進める中で、有線、無線での様々な通信技術が必要となり、通信技術に詳しくなっていきました。現在では大手テーマパークのパレードで使われる車に情報を送るような機材の導入、といった実績もあります。
小泉: 装置やネットワークの機器が作れるということなのですが、ソフトウェアの開発はどうでしょうか。
小田: 高速道路でいうと、サービスエリアのクルマが駐車場にどれくらい埋まっているかを可視化するソリューションを、画像認識AIの技術などを使って開発しています。

また、鍵の遠隔管理・監視システムも開発しました。
自動で鍵を開閉できるシステムで、管理者は遠隔から監視することができます。問題があった際には、遠隔から鍵の開閉が行えます。
小泉: インターネットで使うようなIT系の技術と、電子錠など設備を動かすような制御装置の技術が一社で実現可能なのですね。
小田: おっしゃる通り、こういったところが社内で完結していることで、スピード感もあるという点が強みだと考えています。
「本当のニーズ」を見つけ、形にしていく
小田: また、バロ電機という子会社では、50年近い製造現場におけるノウハウの蓄積があります。
最近作った面白いものとしては、「ちょうちん自動谷折機」があります。
小泉: ちょうちんですか?
小田: はい。全て手作業で行っていた、ちょうちんの折り目をつける作業を自動化するというものです。これまで1つに5分かかっていた作業を、30秒まで短縮することができました。

まずは、手回しの機械から始まり、そこから電動化していきました。そしてセンサーを取り付け、7種類のちょうちんの大きさを自動で把握できるようになり、最終的にはちょうちんを置くだけで自動的に折ってくれます。
小泉: オーダーメイド品を作れるのは素晴らしいですね。
小田: 他にも、TD衛星通信システムという子会社では、衛星システムを作っています。
昨今、災害時BCPが話題になることが多いですが、地上で非常事態が起きても衛星であれば通信ができます。
実際に熊本の大地震の際には、自治体が連絡を取り合えなくなるという事態が発生しました。そこですぐに車に装置を積み込み、電話や通信が使える環境を構築したという事例があります。

小泉: こういった様々な経験が御社の強みとなり、行いたい目標や課題が明確でも、様々な手法での進め方を選ぶ、ということが実現できるわけですね。
岡田: そうですね。課題解決や目標の実現のために、やるべきことを一緒に考え、本当の問題点やニーズを抽出していくことが信頼関係を構築する上でも重要なポイントだと思っています。
また、開発の段階ではお客様の要望の先まで見越し、予め後々便利なシステムを作っておく工夫などもしています。
例えばちょうちんの事例であれば、一日に何個どのサイズを折ったかというデータを可視化できる仕組みを先回りして構築しました。
そうして期待以上の結果を出すことでリピートに繋がったり、他の工場を紹介してもらったりと、新たな展開に繋がっています。
小泉: 本日は貴重なお話をありがとうございました。
無料メルマガ会員に登録しませんか?

現在、デジタルをビジネスに取り込むことで生まれる価値について研究中。IoTに関する様々な情報を取材し、皆様にお届けいたします。