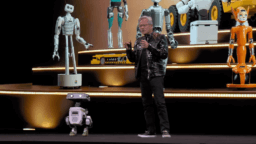ERPに対する、日本と欧米の考え方の違い
小泉: そして、今はIoTの時代です。ERPのシステムにIoTによって取得したリアルタイムのデータを組み合わせていくことが重要になってくると思います。そうした取り組みは世界でどれくらい進んでいるものなのでしょうか。
鍋野: まず、欧米の企業と日本の企業ではERPに対する考え方が異なります。国民性の違いによるものだと思いますが、日本の場合は、とにかく失敗せず確実に進みたいと考えます。そのため、まずは社内のいちばん身近なところの課題解決にシステムを使おうとします。いわゆる、カイゼンやボトムアップといわれる日本ならではのアプローチです。
ところが、欧米は逆です。せっかくシステムを活用するなら、チャレンジをしよう、お金に変えようと考えます。

小泉: それは、具体的にどういうことでしょうか。
鍋野: 日本と欧米では、仕事のパフォーマンスに対する評価の仕方が違うことが背景にあります。日本の場合、与えられた仕事をしっかりこなしたかどうかが成果になります。それに対して、欧米は新しいことをしかけた人が評価されます。最終的に行きつくところは同じなのかもしれませんが、スタート地点が異なるのです。
小泉: なるほど、情報システムの活用によって、最終的には同じところにむかうものの、そこにむかう道筋が違うと。
八子さんもこれまで外資系企業につとめ、様々な企業のコンサルティングを手がけてこられましたが、デジタルの活用という面において、違いを感じますか?
八子: 日本と欧米の違いにおいて、ERPはとくに典型的だと思いますよ。ERPは「エンタープライズ・リソース・プランニング」という名前にあるように、「計画に資するために色々な情報を集める」ということが目的です。それなのに、結局は実績管理にしか使っていない、というのが日本です。
鍋野さんのお話にあったように、欧米は実績の管理をしたうえで、そこから新規事業の検討や次年度のプランニング(計画)に活用しようとします。発想が違うのです。日本は過去のことを見るためにERPを使っているわけです。
小泉: 実績のデータを見て、過去をふりかえるというのは、イメージしやすいです。一方、未来にむかってERPを活用するというのは、具体的にどういうことなのでしょうか。
次ページ:計画を立てるためにERPを使う欧米企業
無料メルマガ会員に登録しませんか?

技術・科学系ライター。修士(応用化学)。石油メーカー勤務を経て、2017年よりライターとして活動。科学雑誌などにも寄稿している。