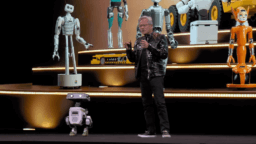今後の戦略
IoTNEWS大藤:今後の戦略を伺いたいのですが。
高田:コンピュータやSIのお金の流れを見ていくと、サービス提供型に変化しています。あるいは人が減っている中でGDPを維持しようとすると、人やサービスの部分がどんどん変化していくと思います。そうすると、より具体的なサービスの部分にNECの売り上げのポーションをどこまで作っていけるのか、という話になるはずです。
これについてはNEC単独ではなく、行政・大学・地域の企業、様々なファイナンスの手法を使って自分たちの立ち位置を変えながら作っていくものだと考えています。
小泉:マイクロサービスに再利用性があるのかが、やはり気になっています。御社にとってはノウハウの溜まっているものだし、他のところでも使えるものであればサービス化し易いですよね。
高田:そこはかなり丁寧に取り組んでいます。使ってもらってフィードバックを得ていって、データが集まる仕掛け、そのデータが次につながるようなダブルループ、トリプルループのような流れを意識していますね。
小泉:数年前に「Orchestrating a brighter world」の話を伺ったのですが、その時に構造化していかなくてはならないという話と、水平に作れるようきちんといなしていかなければならない、ということを社内全体としてやっていく、という話をされていて、割とその話に近づいている印象を受けました。
高田:そうですね。アーキテクチャは概念図に近いものですが、本当に実務で使えるレベルまでにどう落とし込んでいくのか、ということが重要です。その中で協調領域として皆さんに使ってもらえるところを、どこまでNECとしてオープン化するか、というのも戦略的に捉えるべき部分だと思っています。
小泉:プラットフォーマーの方々は共創領域の線引きについて熟慮されていますが、「FIWARE」も同じではないか、と思っています。オープンだからといって、何でもオープンにするわけではないですよね。
高田:そうですね。オープンプラットフォームとしての「FIWARE」は世界中で実績はありますが、OSSなのでいわゆる製品として物足りない部分もあります。そこは、NECが様々な実績経験とともにOSSを活用する能力や技術力を組み合わせて地域実装を支えていくことで独自の価値が出せると部分だと考えています。実際それが役に立って、誰かがお金を払う価値にならなければ、持続していかないわけですから。
小泉:ヨーロッパは社会課題に対する取り組みに応援してくれるような風土がありますが、日本は割とそういう方向ではない気がします。
ヨーロッパは社会課題に対して企業が投資を行いますし、市民もそうした方がという方向に流れがちだと思うので、ぜひこのスペインを中心とした地域で取り組んだノウハウを日本に持ち帰っていただければ、と思います。
高田:スマートシティをマーケットとして捉えたときのイノベーターは誰だ、ということを考えるのが重要だと思っています。
そうしたリーダーシップを発揮できるイノベーターとマーケットを上手に作っていき、市民にも参加してもらって自分の街を良くしていくという意識を持ってもらう。シティラボの先進的な地域は市民が参画するマインドが全然違いますよね。そういったものを醸成していくのは大切だと考えています。
小泉:本日はありがとうございました。
無料メルマガ会員に登録しませんか?

1986年千葉県生まれ。出版関連会社勤務の後、フリーランスのライターを経て「IoTNEWS」編集部所属。現在、デジタルをビジネスに取り込むことで生まれる価値について研究中。IoTに関する様々な情報を取材し、皆様にお届けいたします。