MWC2023レポートの第5弾は、海外キャリアレポートだ。
MWCには多くの通信事業者が出展している。サムスンやクアルコムなどの主要企業が集まるHall3には、ボーダーフォンや、ドイツテレコム、テレフォニカ、オレンジ、SKテレコムなどが例年出展していて、今年も同様の顔ぶれだった。
ボーダーフォン
日本でもサービスを提供していた時期もあるボーダフォンは、現在欧州各国で通信サービスを提供している。
昨年スタートした「SwitchToGreen」キャンペーンがブースのエントランスにあった。
通信事業はどの国でも多くの電力を消費するビジネスであるため、環境対策は共通のテーマでもある。
事業運営に直結する電力消費の効率化はもちろんだが、「SwitchToGreen」の中で注目したいのはEco Ratingの仕組みだ。

これはVodafoneだけでなく、Orangeやドイツテレコムなどとも協力し、SamsungやOPPO、HUAWEIなどのメーカーと共に取り組んでいるものだ。
スマートフォンや携帯電話の販売時に、それぞれの機種の持続可能性を可視化するもので、本体の耐久性や部品のリサイクル度合い、バッテリーの持続性、修理対応力など19の視点で評価されているという。
ドイツテレコム
5Gらしい機能として期待されているクオリティ・オン・デマンドも展示されていた。
目的や用途に応じた通信の最適化と、最適な通信を担保するネットワークスライシングを活用したものだ。
バーチャルな専用線のように提供すると、ダイナミックな運営が難しくなる。ユーザー体験を考えるとユーザー側での設定などはせずに、自動で最適化が望ましい。また通信事業者視点では個別最適しながら全体最適を実現したい。
このようなニーズに対応するのがクオリティ・オン・デマンドだ。ドイツテレコムブースでも展示されていて、5Gの快適性を大きく向上させるものとなるため、高い注目を集めている。

ブースでは、解像度が異なる2つの映像があり、それぞれの配信に必要な通信スペックを設定しているデモが行われていた。ネットワークが用途踏まえた通信の実態を把握することで、それぞれに必要となる通信スペックを設定し、維持するというものだ。
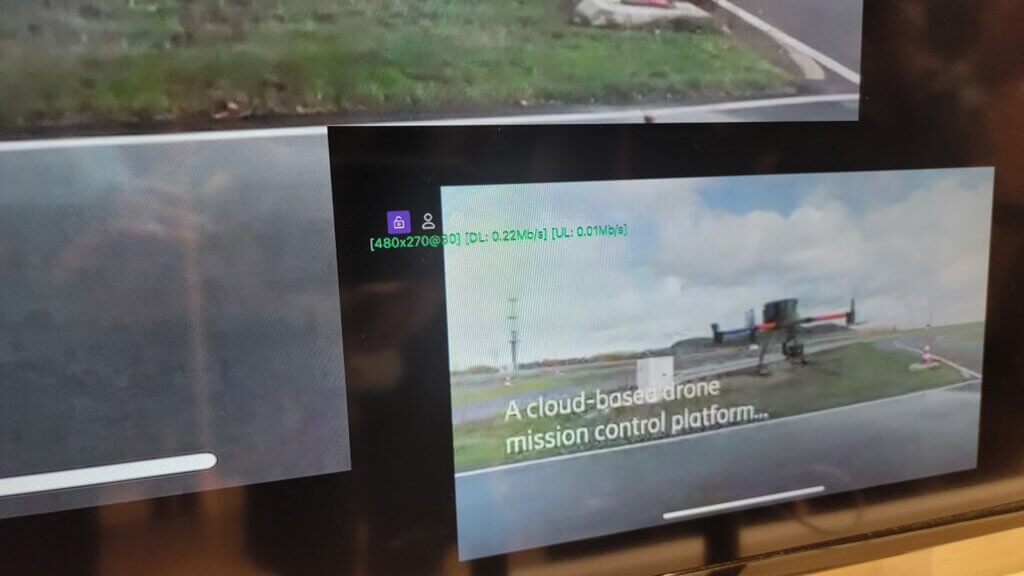
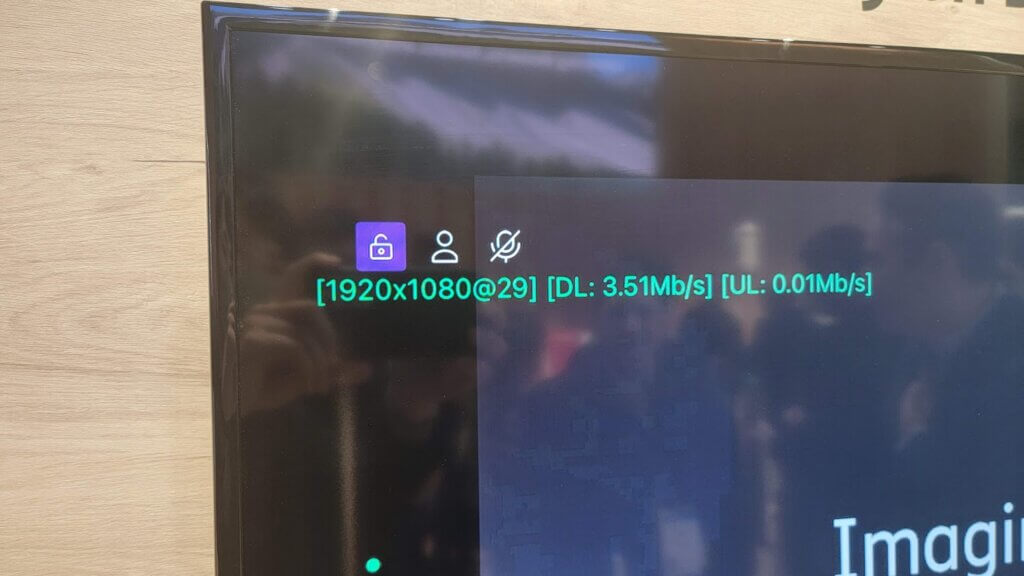
マゼンタピンクがトレードマークのドイツテレコムブースでは多次元ネットワークの展示があった。これも新たなトレンドの1つだ。
地上波でカバーできない部分も含め、地球上の全てで通信ができるようにしていくためのアプローチとなる。これまでの携帯電話、スマートフォンの電波は地上波で通信エリアをカバーしている。

それに対し成層圏プラットフォーム(HAPS)や低軌道衛星(LEO)、静止衛星(GEO)などはNTN(Non-Terrestrial Network:非地上系ネットワーク)と呼ばれ、地上波ネットワークとは別の衛星通信サービスを提供している。
多次元ネットワークはNTNを独立した衛星通信ではなく、地上波を空中から出力する基地局として活用し、既存の地上基地局では圏外になっているエリアをカバーするものだ。
例えば山間部など、地上基地局からの電波が届かない場所へは、地上基地局から衛星や成層圏の基地局に向けて通信し、NTNを介してモバイルデバイスへ通信サービスを提供する。
つまり、HAPSや衛星が地上ネットワークの中継局となる考え方だ。
クアルコムがスマートフォン向けの衛星電話機能を5Gモデムと併存できるように提供するという発表もあり、地球全体のシームレスカバーに向けたNTNと地上ネットワークの連携が加速していくことになりそうだ。
エアバス
ちなみに今回はエアバスも出展していて、ブースには成層圏も飛べるソーラーUAVが展示されていた。
このUAVは成層圏プラットフォーム「HAPS」で空中基地局として機能する。ドイツテレコムとAirbusはフラウンホーファーやミュンヘン大学などとAir Mobility Initiativeを結成し、関係各社と共に多次元ネットワークのPoCを進めている。

5Gはこれからさらにネットワークのインテリジェンスが向上し、ユーザー体験からストレスが減っていくことが推察される。また空が見える場所であれば、専用の衛星電話を必要とせず、どこでも通信ができる未来も見えてきた。
無料メルマガ会員に登録しませんか?

未来事業創研 Founder
立教大学理学部数学科にて確率論・統計学及びインターネットの研究に取り組み、1997年NTT移動通信網(現NTTドコモ)入社。非音声通信の普及を目的としたアプリケーション及び商品開発後、モバイルビジネスコンサルティングに従事。
2009年株式会社電通に中途入社。携帯電話業界の動向を探る独自調査を定期的に実施し、業界並びに生活者インサイト開発業務に従事。クライアントの戦略プランニング策定をはじめ、新ビジネス開発、コンサルティング業務等に携わる。著書に「スマホマーケティング」(日本経済新聞出版社)がある。



















