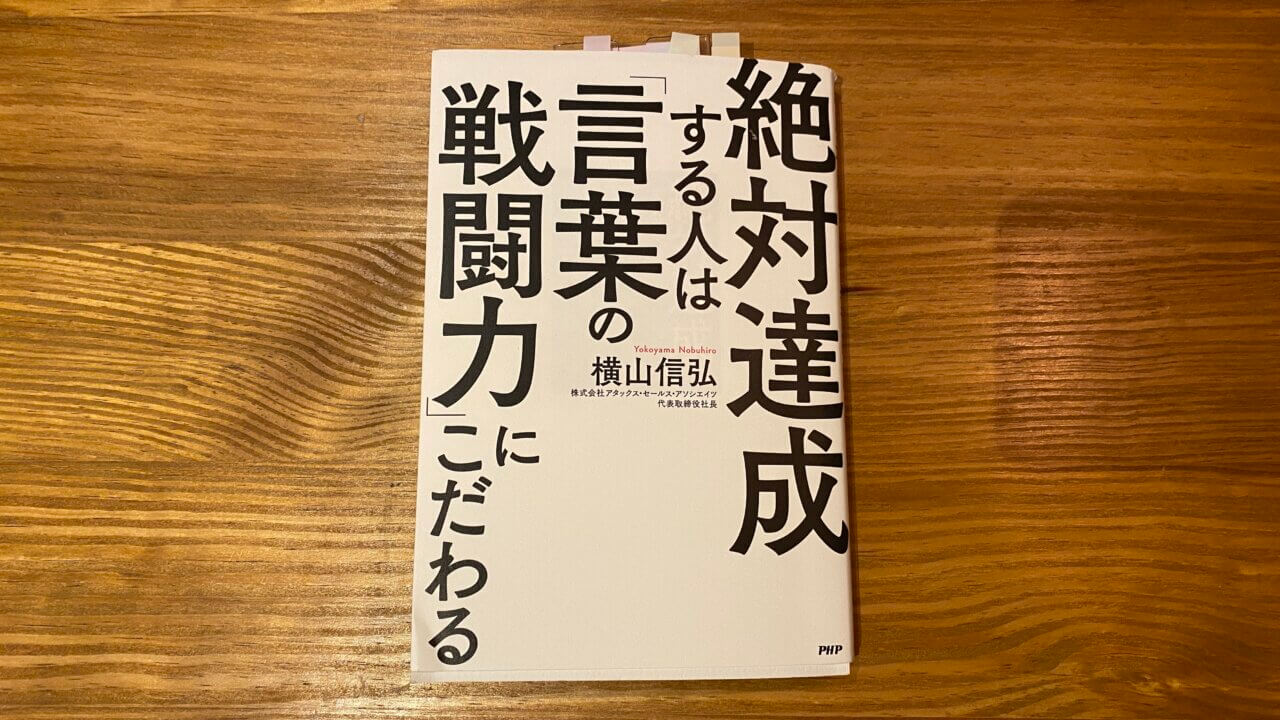書評コーナーでは、私がDXプロジェクトで、「よくある課題」を解決するヒントになる内容があると感じた書籍を紹介していきます。
なぜ、この本を紹介するか
この本は、「言葉の持つ力」について書かれているのですが、私自身が普段、DXをテーマにした企業向け勉強会を行っていて、多くの方から質問される、「デジタルを使いこなすための企業文化の変革」と言うテーマについて、示唆に富む内容があったので紹介したいと思いました。
「社員のデジタル音痴」「デジタル技術導入に対する反発」「仕事を変えたくない」など、DXを推進する方にとって、一番頭が痛いのが、社員のデジタルリテラシではないでしょうか。
DXを推進する方は、多くの部門や関係者の理解を得たり、進めたりするために、人材掌握術を磨く必要があります。
すべてのDXプロジェクト推進担当や、マネージメント、リーダーになった方に読んでいただきたい本です。
この本の解説
この本では、モチベーション、働きがい、PDCA、イノベーション、主体性、褒める、楽しむ、論理的といった、「8つの言葉」について、「絶対達成する人と」、「絶対達成できない人」の特徴や振る舞い、考え方など、さまざまな視点でその特性を掘り下げ、さらに、絶対達成するにはどうしたら良いか、という方法論を説いています。
「モチベーション」を言い訳にしてはいけない
一つ目の言葉は、「モチベーション」です。
やるべきことをやるのに「モチベーション」は関係ない。私はこの言葉には大賛成です。
モチベーションとは、「あたりまえのことを、あたりまえにやるだけでなく、それ以上の行動をとるために必要な心の動き、意欲、動機付け」なのです。
つまり、「モチベーション」を議論する前に、まずは仕事における「あたりまえ」が何かを議論することが重要なのだと書かれています。
当たり前が明確でない組織においては、それ以上の行動も定義できないので、モチベーションについて議論することができない。
仕事ができる人は、モチベーションが高いから仕事ができるのではなく、常に「あるべき姿」を正しく認識していて、現状との間にあるギャップを埋めようと自然に体が動く。なので、どんどん仕事の目標を達成していく人からすると、それは「すごいこと」ではなく、体が勝手に動くから「あたりまえ」なのだと言う訳です。
こういう状態に持っていくことができれば、あたりまえのことは、当然達成することができ、それ以上の行動をとる人がさらなる到達点へと向かうような組織がつくれるというわけなのです。
どうでしょう。結構初めから難しいことを言ってますよね。
みなさんは自分の仕事の「あるべき姿」を描けていますか?
「PDCA」を回していこうと唱えるだけでは、回らない
次の言葉は、「PDCA」です。
PDCAという言葉は、Plan, Do, Check, Actionの4つの頭文字を取った用語で、知らない人はいないくらいメジャーなキーワードでもあります。
それゆえに、「PDCA、PDCA」と掛け声のように唱える人も多いのですが、唱えていても意味はない。
本書によると、PDCAの中で、一番大事なのは「P(計画)」だとしています。
そして、計画を立てる上で、何よりも必要なのは「問題設定」だと。
なぜなら、PDCAで継続的に改善すべき「問題」が正しく設定されていないと、なにをやっているのかわからないことになるからです。
PDCA回せ!はいいけど、Dから始まっているプロジェクトをよく見かけます。「とりあえず、ペーパレスにする」とか。でも、「何のためにペーパレスにするか」が明確じゃないと、プロジェクトの評価も継続的な改善もどこに向かえば良いかわからないですよね。
ここで言う、「問題」というのは、「あるべき姿」と「現状」の間の「ギャップ」です。
「問題」が設定できたら「なんの目的で」「どのタイミングで」「誰が」「どのような方法で」解決するのか、どういう「目標」を立てるのか、という「P(計画)」が立てられるわけです。
例えば、「目的」が「DXのための企業文化の改革」といった概念的な内容だとすると、「目標」を数値化するのが難しいと思うかもしれませんが、例えば「オンライン会議システムの利用率を80%にあげる」など、なんらかの数字になる目標をおくとよいとしています。
仮置きの数字でもいいから、なんらか具体的な目標にすることが重要なのですね。
こうすることで、P→DCAが動き始まります。
なぜ、具体的な目標出ないといけないのかと言うと、ここを曖昧にすると、「C(チェック)」の時に、なにを合格としたら良いのかわからないし、「A(改善)」の時に、「P(計画)」で立てた目標の数値や中身を変えれば、また次の「D」に向かうことができる、というわけなのです。
そして、「D(実行)」では、「やりきること」が重要だということです。
なぜなら、問題解決のために立てた計画をやり切らないと、そもそもその計画が良かったのかどうかも評価できないからです。
DX推進プロジェクトでは、始まると現場ができない理由を並べ始めて、結局プラン通りやらずグダグダになるというのを見かけますが、計画時点でコンセンサスが取れていないと言うことなのかも知れません。
いずれにせよ、与えられた問題を解決するのが得意な日本人、問題を自ら定義した習慣がない人にとっては、まずは問題を明確にし「P(計画)」を立てるところが最も重要で難しい、となりそうです。
「イノベーション」を起こそうといってるだけでは、何も起きない
続いては、「イノベーション」です。
「もっとイノベーションを起こせ」「イノベーションを起こさないと明日はない」という掛け声を聞くことがよくあります。
しかし、当たり前のことですが、掛け声をかけていても何も起きないし、「イノベーション推進部」などを作ったところで、イノベーションは起きません。
最近のDX推進部の作られ方をみていると、数年前にイノベーション推進部を作った時と同じノリな感じがして、ちょっと嫌な気持ちになることもあります。
イノベーションには、そもそも「JUMP」と「SHIFT」の2つの種類があるのをご存知でしょうか。
「JUMP」については、みなさんがイメージしているような、これまでのビジネスモデルやビジネスプロセスを大きく壊してでも新たなビジネスを産みだそうとするものです。また、「SHIFT」は、既存のビジネスモデルやビジネスプロセスの強みを理解して、アップデートすることです。
「SHIFT」の方が一見簡単そうですが、実は「現状維持のバイアスがかかりやすい」という意味で、抵抗勢力が出やすいという特徴もあります。
ただ、多くの企業において、「いきなりJUMPと言われても・・・」という方が多く、SHIFTを採用されるケースが多いという実態があります。
私の考えとしては、「外部環境が大きく変化する場合はJUMPも必要」としています。
よくある例ですが、馬車の社会から車の社会に変化したら(外部環境の変化)、これまでやっていた事業がそのままではやっていけなくなる、といったような状況です。

ところで、イノベーションを実現する際には、「どういうアイデアを採用するか」ということが大きなテーマとなりますが、この「アイデア出し」が簡単ではありません。
そこで、本書では具体的にアイデアを生み出す方法論として、
- ポアンカレの4つの思考プロセス
- オズボーンのチェックリスト法
- SCAMPER法の7つの問い
- 4W2H
- 創造性の4B
- ディズニー・ストラテジー
といったビジネスフレームワークも紹介しています。
これ以外にも、本書には度々ビジネスフレームワークが登場するので、頭を整理するのに役立ちます。
自分のことを「論理的」と言う人ほど、論理的ではない
プロジェクトを推進する際、周りの状況を理解したり、必要であれば説得したりする必要があります。
例えば、「仕事のやり方は変えられません」という現場のメンバーに対して、「どうしてですか?」と聞くと、「このやり方が一番効率的だから」と言われてしまうことがあります。
こう言う人は、最初から結論(仕事のやり方は変えたくない!)が決まっていて、そのために都合の良い根拠(一番効率的)を持ち出し、自分の主張を通そうとするものです。
そもそも、そのやり方しかないと主張する人が、「一番」効率的かどうかなんて、判断できるわけもないのに・・・。
また、会話をしていて、「根拠がありそう」な話し方をする人にも要注意です。
例えば、「売り上げ向上のためのキャンペーンをやろう」と言い出した人がいるとします。
その人に対して杓子定規に「キャンペーンなんかにお金を使うのではなくて、売上が上がらない根拠をまずは調べて、総合的に解決策を練るべきだ」というような人がよくいます。(コンサルにもよくいます)
一見するともっともらしいのですが、こう言う人の言うことをいつも聞いていると、何もできなくなり、無駄な時間が流れてきます。
こういう「根拠がありそう」な話し方をする人は、「なぜ売上向上のためにキャンペーンをやろう」としているのかについては、まったく耳を傾けもしないで、自分の考え方を押し付けようとします。
自分の中で、「キャンペーンなんて意味がない」とでも決めているからかも知れませんが、こういう手合いは、正論をぶつければ良いと思っているようにも見えます。
論理的「風」な人は、理屈を並べるけど、全体と部分の因果関係や部分と部分の因果関係が明確になっていない場合が多い、と本書では書かれています。
キャンペーンの例では、これまでどういうキャンペーンをやってきたのかを聞くべきだし、もうすでに話が進んでしまっていて戻れない状態かも知れない、という想像力を働かせることも重要です。
こういう相手の状況を理解しようとしていれば、会社全体としての売上向上のための動きを理解することができ、なぜ、この人はキャンペーンをやろうとしているのか、これからどうしたらよいのか、という建設的な議論が進められるたはずです。
プロジェクトや組織を動かすには、そこにいる人を動かす必要があるわけなので、全体と部分、部分と部分の因果関係を明らかにすると、施策の優先順位がはっきりしたり、コミュニケーションの質が向上するということなのですね。
また、昨今社会がとても複雑になってきて、論理的なだけでは解決できないことが多くなってきました。
こういう社会では、論理思考だけでなく、「直感力」も必要になります。
論理力がある人は、ものごとを分解して、分析することができます。その一方で、直感力が高いと、バラバラとあるものをうまく「抽象化」することができるのです。
抽象化することによって、物事のパターンや法則を見破ることができる。その結果、毎日の中でさまざまなポジティブな発見ができるようになるということです。
感想
最近、従業員エンゲージメントや働きがい、など、耳障りのよい言葉が増えています。
しかし、DXを推進する上では、デジタルを使いこなせる企業文化を変え、メンバーを動かし、事業そのものをSHIFTもしくはJUMPさせなければなりません。
今回紹介した内容では、当たり前ですが、本書の良さをすべてあらわせているわけではありません。ぜひ、今回紹介できなかった言葉についても筆者の考えを参考にしてください。
言葉に逃げず、言葉と向き合って、現場の意識改革を進めることがDX推進における要所だと感じました。
無料メルマガ会員に登録しませんか?

IoTNEWS代表
1973年生まれ。株式会社アールジーン代表取締役。
フジテレビ Live News α コメンテーター。J-WAVE TOKYO MORNING RADIO 記事解説。など。
大阪大学でニューロコンピューティングを学び、アクセンチュアなどのグローバルコンサルティングファームより現職。
著書に、「2時間でわかる図解IoTビジネス入門(あさ出版)」「顧客ともっとつながる(日経BP)」、YouTubeチャンネルに「小泉耕二の未来大学」がある。