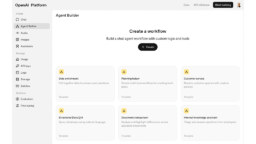VRの“没入感”は仕事に必要?
小泉: 『マトリックス』(1999年に公開されたアメリカ映画)などの映画にあるように、バーチャル空間の中にヒトが入り込み、そのリアリティが高まってくると、リアルの世界にいるのか、バーチャル空間の中にいるのかといった、区別がつかなくなりますよね。
映画の世界だと「ほう」と思っていたのですが、実体験してみるとそのような感覚に近く、操作に慣れてくると、あまり手足を動かすことに違和感がなくなってきます。
つまり、バーチャル空間の中がかなり”器用”になっていて、モノをつかんだり広げたりすることが自然な操作としてできるようになっているのです。
自分が思ったことを、(バーチャル空間で)すぐにできてしまう。そうなってくると、仕事の環境も変わってくると思います。
八子: 我々は、ハノーバーメッセでVRアーティストの「せきぐちあいみ」さんのパフォーマンスを見ましたね。
小泉と八子は、4月23日~27日にドイツのハノーバーで開催された世界最大の産業見本市「ハノーバーメッセ」を訪問していた。
VRゴーグルを使い、3D空間上で彼女が描いたものを我々は(ゴーグルをとおして)ずっと見ていましたけれども、あれは”没入感”ならではこその操作感かつ素晴らしいグラフィックが可能になるわけで、パソコンのこちら側にいると(ユーザーインターフェースがVR空間の外にある場合)、なかなかあそこまでのものは描けないのかもしれませんね。
ただ、私も最近、自宅で「Oculus GO」を使い、色々なコンテンツを見ていますが、2時間も見ているとかなり脳が疲れてくるというか痺れてきて、つけたまま寝てしまう時があります(当然、デバイスの電源は切れています)。
小泉: 普通に疲れているだけじゃないですか(笑)。
八子: いやいや(笑)。元々疲れているのもありますが、長く見ていられないのです。
ですから、たとえば先ほどのようなVR空間上で、8時間ずっとCADの画面を見ながら、議論や作業を続けるということができるのかな、というのは思います。
小泉: 私は、リアルな世界でパソコン作業をすることと、バーチャル空間の中で没入して何かをすることは、使い分けることができるのかなと思っています。
例えば、会議などをとおして(会議そのものは無理にバーチャル空間でやる必要はないかもしれませんが)、出来上がってくるモノ(製品)の過程をメンバーと共有したり、写真とか立体物を見ながらイメージを共有したり。
文書で伝えるのではなく、活字よりもわかりやすい「イメージ」を使って訴求していくということができると思います。

次ページ:テクノロジーが職場に普及しない理由
無料メルマガ会員に登録しませんか?

技術・科学系ライター。修士(応用化学)。石油メーカー勤務を経て、2017年よりライターとして活動。科学雑誌などにも寄稿している。