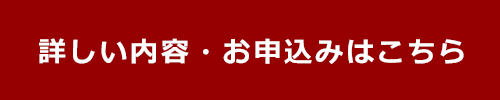製造業におけるキーワードの一つとして「デジタライゼーション」という言葉がある。
「デジタル化」と何が違うのか?と思う方もいると思うが、実は大きく異なるのだ。
デジタル化は、これまでできていたことをデジタルに置き換えることで、その結果「自動化」や「高速化」といった恩恵を受けることができる。これは、インダストリー3.0とでもいうべき内容で、多くの方にとって馴染みにのあることだ。
その一方、「デジタライゼーション」は、IoTによって生産におけるプロセス全体をデジタル化することで、バーチャル空間上にリアルの状態のコピーとなる「デジタルツイン」を構成し、デジタルツインがあることで未来を予測するようなシミュレーションを行うことができるのだ。
実は、国内における単純なIoTの解説では、一つの「モノ」に着目して語られることが多いため、例えば「ラインを構成する一つの産業機械」をネットワークに接続することで、「産業機械の稼働状況」を可視化する、といった利用シーンが語られることが多い。
しかし、インダストリー4.0などの概念モデルではこういった単純なことだけを語っていない。
一つの産業機械に注目するだけでなく、一つのラインを構成する「すべての産業機械」の状態をネットワークに接続することで取得し、デジタルツインに展開されたバーチャル空間上でラインを動かす。産業機械のコントローラーの動作もデジタルツイン上で再現するのだ。
そうすることで、生産そのものをデジタルツイン上でシミュレートすることができるので、通常、実際のラインで試してみては設計をやり直すというプロセスを繰り返すオーバーヘッドが起きるところを、極小化することができるのだ。
例えば、ドイツのeGOという電気自動車の企業では、設計から製造までのプロセス全体をデジタルツイン上に展開し、衝突の際ドアの凹みがどうなるかなど、通常リアルで行うことをすべてバーチャルで行い、デザイン的にも理想的な形を設計したら、今度は生産の現場でその形が実現できるのかをシミュレーションする。
こうやって、膨大な時間とコストのかかる、生産における改善の繰り返し作業をデジタル上で行うことで、極めて生産性の高い製造が可能となるのだ。
eGOのように、「設計・製造」のみならず、販売や顧客が受け取る体験までのプロセス全体をデジタル化し、未来を予測しながらシミュレーションした結果を、生産の現場に返すというやり方が「デジタライゼーション」なのだ。
顧客の購買行動が激しく変動している昨今では、一つの製品を製造するのに時間とコストをこれまでのようにかけている場合ではない。
6/15(金)に開催される、IoTNEWS主催、IoTConference2018では、「デジタライゼーションが作る未来とそれを支える技術」について、有識者の方にご登壇いただき、解説していただきます。
詳しい解説ページに遷移します。
無料メルマガ会員に登録しませんか?

IoTNEWS代表
1973年生まれ。株式会社アールジーン代表取締役。
フジテレビ Live News α コメンテーター。J-WAVE TOKYO MORNING RADIO 記事解説。など。
大阪大学でニューロコンピューティングを学び、アクセンチュアなどのグローバルコンサルティングファームより現職。
著書に、「2時間でわかる図解IoTビジネス入門(あさ出版)」「顧客ともっとつながる(日経BP)」、YouTubeチャンネルに「小泉耕二の未来大学」がある。