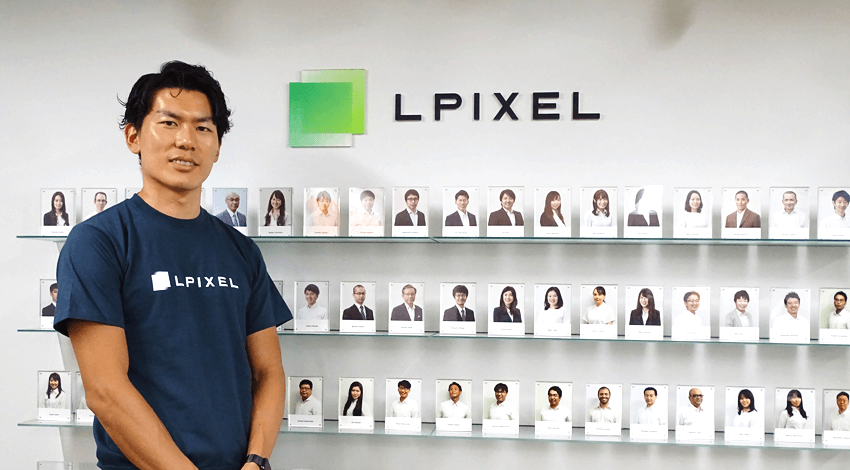医療機器とリスク管理
石井:医療機器はリスクをどう低減していくのかが課題になると思っているのですが、実際に開発するなかではどういったリスクが想定され、どう潰していったのでしょうか。
島原:当然リスクはあるという前提でリスクを上回るメリットがある、と示すことが大事です。薬にしても副作用などリスクがあるわけですが、だからすべてやめましょうとはなりません。それよりも救われる人が多いからやりましょうとなることがあるわけですが、そういう意味では、リスクを上回るメリット(効果効能)を実証できるスタディ(治験や臨床試験)が必要になるかと思います。
AIを使用することで感度(検出率)が10%くらい上がり、全体最適につながります。医療は全体最適で考えることが多いので、リスクは絶対にあるけれど、それを上回るメリットがあると示すことが重要になります。
これには答えがあるわけではなくて、一つ一つ理論に基づいてやっていく必要がある。なので薬事というのは結構クリエイティブな仕事だなと思っています。法規制対応というと、少しめんどくさい、専門知識や資格のある方が一定の決められた項目に沿って対応するというイメージがあるかと思います。もちろんそういったドキュメント管理などもありますが、薬事を通すところというのは実はかなりクリエイティブ。何がメリットでどこまでのリスクがあって、リスクを上回るメリットがこうだということを構築するというクリエイティブな仕事なのです。難しいですが、面白さもあります。
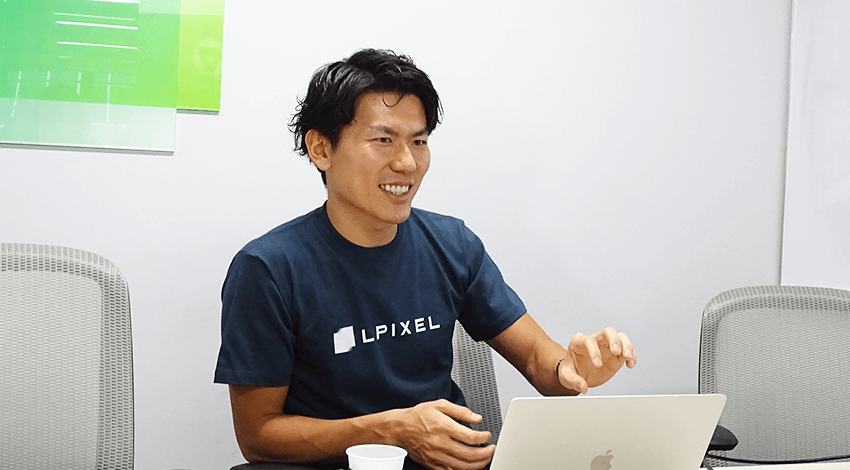
「EIRL」の臨床試験は「後ろ向き」に行うことも
石井:薬の治験はイメージが出来るんですけど、AIの医療機器プログラムの治験はどのように行うのでしょうか。
島原:治験というのは大きく分けて「前向き」か「後ろ向き」というのがあります。「前向き」というのは薬でよく言われる方法でして、治験者を集めて、薬を投与して、半年間様子を見ましょうといったもの。デザインしてから集めるという工程を踏むのですが、一方、放射線画像診断の場合は「後ろ向き」のスタディが多く、過去に取ったデータを集めて医師で試験デザインを組んで実施するというものです。まずはデータを集めて、異常のあるものを定義し、複数名の医師が合同で正解データを作ります。その後、試験に参加いただける医師の方に来ていただいて、そのデータをもとに読影試験をします。
現在でもそういった試験を実施しており、土日などにも来ていただいてます。医師がオリジナル画像を見て、そのあとでAIによる結果を確認する。そこで、医師による最初の診断結果とどう変わったかを比較するという試験をやっています。したがって、医師側には工数がかかっていますが、患者さんへの負担はありません。
石井:治験というと数億円ほどかかるというイメージがありますが。
島原:薬の治験を行うには薬代の他に、治験に協力いただく方へ副作用があるかもしれないのでそれに見合った報酬を差し上げる必要がありますが、我々が行なっている試験では患者さんに直接副作用等が及ぶわけではないので、医師やスタッフの人件費などがメインとなり、およそ数百~数千万円です。
大事にしたのは新しいことをやるためのチーム作り
石井:医療機器の承認を得るまでにはいろんなプロセスがあるかと思いますが、どの点で苦労されたのでしょうか。
島原:開発に協力いただける医師に出会うことがまず最初の課題でした。これがないと始まらない。僕自身は医師ではないですし、創業時から会社に医師がいたわけでもないので、自分で便利なものを作ろうというよりは、この方の役に立ちたい、という人がいることが重要なのです。そういう意味では、最初に会った先生は先進的なこととか、役に立つことというのを熱心に語られる先生で、まずこの先生の為にAIを作ることから始まりました。そうしたら、いいねと言っていただき、プロトタイプを作成することになりました。
先生が使っているビューワー上にハイライトされるものを最初に作ってみたり、三次元の立体に瘤があるというのがわかるようなものを数か月かけて作成しました。これを作ってみたらとても喜んでいただきました。そこから、ミッション化し、この先生を救うために頑張ろうといったように後はなんでも乗り越えられるという感じでした。そういうチームを作れたのは幸運でした。
また、薬事が大変でした。最初は半年ほど各行政機関回りをしたのですが、門前払いをされることもありました。話が通じないので薬事コンサルを連れて来てください、と言われたこともあります。ソフトウェア医療機器は新しいものなので、社会全体を見渡してもわかる人がほとんどいない状況で法規制対応するチームを立ち上げなければならなかったのです。
ベンチャー企業で、クラスⅣ(ペースメーカーなど高度な管理を要する医療機器)というかなり難しいランクの製品を通した会社があって、そこはどうやって通したのか聞いたところ、最初はコンサルをあたったけど上手くいかず、結局新しいことを通すには自分たちでやるこことが必要だ、と。クリエイティブな仕事になるので自前でそういうチームを作らなければだめだ、と言っていました。それを聞いてハッとして自社でチームを作ってやったというのが大きいですね。
いいものを作るのが得意な人はたくさんいると思うのですが、それを世の中に通すための法規制対応というのはまた違うスキルになるので、そういったところは他のベンチャーでも課題になるのかなと思います。
小泉:本日はありがとうございました。
無料メルマガ会員に登録しませんか?

現在、デジタルをビジネスに取り込むことで生まれる価値について研究中。IoTに関する様々な情報を取材し、皆様にお届けいたします。