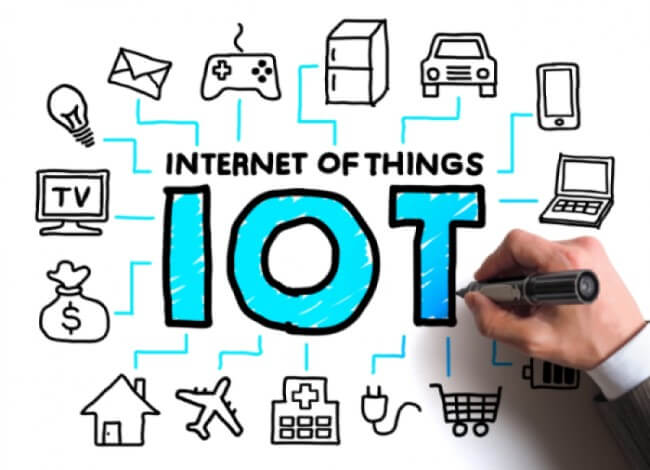調査会社のIDCJapanによれば、日本国内のIoT市場規模は、2018年はおよそ6.3兆円だという。IoT市場はますます拡大を続け、2023年にはおよそ12兆円規模に達するという試算もある。
こうした現象は日本国内の現状に限らない。
同機関によれば、2018年の世界のIoT市場規模は6,460億ドルで、1ドル=108円で計算すると70兆円になる。2022年には1兆ドルに達する予測だ。
ここで読者に押さえてもらいたいのは、IoT経済の規模感をつかむことよりも、こうしたIoTのひろがりが流行語やバズワードといった言葉で説明されるような一過性の現象では無いということだ。
また、モノとモノがインターネットでつながることによって、産業構造のみならず、わたしたちのワークスタイルやライフスタイルも変化していく。
このような背景があることから、IoTをしらない人、IoTをなんとなくしっている人に向けて、当記事ではそもそもIoTとは何か、という基本を取り上げる。
なお具体的な事例についてはIoTNEWSの事例記事を閲覧していただきたい。
IoTという言葉はいつから?
IoTとは「Internet Of Things」の略でモノのインターネットと訳される。
日本では2016年くらいからIoTという言葉が使われ始めるようになったが、もともとは1999年にケビン・アシュトンというイギリスの技術者が名付けたと言われている。
しかしIoTという言葉が誕生してから、日本で使われるようになるまで、だいぶタイムラグがあることに気づく。
なぜか。
それはIoTを実現するために必要なネットワークインフラが整っていなかったことやセンサーの生産量が今よりも少なく、現在と比べると高級品だったことが理由といわれている。
ありとあらゆるモノがインターネットにつながる
IoTはありとあらゆるモノがインターネットでつながるということだ。
具体的には、センサーによってデータが取得され、クラウドサーバーにアップロードされた後、それらのデータが特定のアルゴリズムに従って処理(プロセス)される。そして最後に解析・判断された結果が人にフィードバックされるというものだ。
もちろんこれらのやりとりは、すべてインターネットを介して行われる。
まとめると、IoTを構成するためには以下の4点が必要不可欠となる。
- センサー
- クラウド
- プロセス
- フィードバック
では、構成要素1つ1つに焦点をあてて説明していく。
センサー
センサーは人の代わりに様々な物理現象を電気信号へと変換し、データを取得する役割を担っている。
代表的なものとしてはGPSが挙げられるが、ほかには磁気センサー、加速度センサー、ジャイロセンサー、環境光センサー、近接センサー、指紋センサー、温度センサー、湿度センサー等がある。
センサーは様々な製品の中に存在し、例えばスマートフォンのディスプレイが周囲の明るさに合わせて自動的に調整されるという機能には、環境光センサーが使われている。
なおセンサーが物理現象を感知してから、データとして取得するプロセスをセンシングという。
クラウド
クラウドは直訳すると雲という意味になるが、ITにおいてはネットワークにつながった先のサーバーを指す。
今では、クラウドは一般的に利用されているが、クラウドが誕生する前は、スマートフォンやパソコンといった機器にデータやアプリケーションが保存されていた。
データやアプリケーションが機器に保存されていると、あるデータが欲しい時やあるアプリケーションを動作させたいときに、その機器でしかアクセスすることが出来なかった。
しかしインターネットの通信速度の発達にともなって、クラウドが誕生し、データやアプリケーションがネットワークにつながった先で利用することが可能となった。
例えば、NETFLIXはユーザーIDとパスワードの入力さえすれば、テレビでもスマートフォンでもパソコンでも利用が可能だ。これはクラウドだからこそ実現できる利便性といえる。
Gmail、LINE、iTunes Storeなどもクラウドサービスとして挙げられる。
では、ローカルにサーバーを構築した状況ではIoTは実現されないのだろうか。
結論からいうと、ローカルサーバーでもIoTは実現することができるが、つながることのできるデバイスの数の上限がサーバーの能力に依存してしまうという問題がある。
多数のスマートフォン、PC、センサー、ゲートウェイを駆使して実現されるIoTの世界においてはクラウドを利用することが一般的である。
プロセス
クラウド上にアップロードされたデータはある特定のルール(アルゴリズム)にしたがって解析・判断される。
ここでは、近年注目されている機械学習やディープラーニングといった人工知能によって解析・判断されるケースもある。
フィードバック
フィードバックは、クラウド上で解析・判断された結果に基づいてモノを制御するということだ。
例えば人の音声によって温度の調節が自由にできるIoTエアコンであれば、音声データを取得後、その音声が「寒い」と判断した場合には、温度を上げるという制御を行う。
これがフィードバックであり、IoTにおいてはこのフィードバックによってその価値が決まると言われている。
IoTの構成要素4つの機能を振り返る
IoTの構成要素は、センサー、クラウド、プロセス、フィードバックと説明した。それぞれが機能する流れについて整理する。
- 取り付けられたセンサーが現実世界の物理現象を検知し、データを取得する。
- インターネットを介して、センサーから送られたデータがクラウドにアップロードされる。
- クラウドにアップロードされたデータがアルゴリズムに則って解析・判断される。
- 解析・判断された結果が現実世界のヒトにフィードバックされる。
Uberで振り返るIoTの基本
タクシーに乗りたい人と空車のタクシーをマッチングするUberはIoTによって実現されているサービスだ。
- スマホのGPS(センサー)がスマホ所有者の位置情報を取得する。
- 取得された位置情報はクラウドにアップロードされる。
- アップロードされた位置情報から、最も近い空車のタクシーが検出(処理)される。
- 空車タクシーのドライバーにたいして、乗車リクエストが通知(フィードバック)される。
近年、スマートファクトリー、スマートロジスティクス、スマートハウス、スマートオフィス、スマートシティといった様々な分野でIoTの活用が進んでいる。
当記事で説明した基本概要を頭に入れておくと、意外と身近なモノがつながっていることに気づくかもしれない。
無料メルマガ会員に登録しませんか?
現在、デジタルをビジネスに取り込むことで生まれる価値について研究中。特にロジスティクスに興味あり。IoTに関する様々な情報を取材し、皆様にお届けいたします。