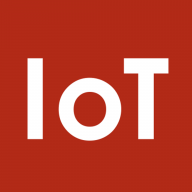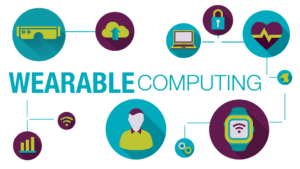現在の光ファイバネットワークでは、1本のファイバの中に、コアと呼ばれる光が通る導波路を1本持つ構造の光ファイバが用いられている。
これに対し、ファイバあたりのコアの数を増やし、光信号を並列に送信することで、空間チャネル数を増やすマルチコアファイバなどによる空間分割多重光伝送の研究開発が進んでおり、伝送容量の拡大を可能とする将来の大容量基幹光ネットワークの基盤技術として期待されている。
既存の光ファイバと同じ細さを保ったまま、空間チャネル数を10以上に拡張するためには、隣接するコア間の光信号を意図的に混信させる結合型マルチコアファイバが有望視されている。
結合型マルチコアファイバでは、信号を受信した後の受信機において、デジタル信号処理と組み合わせることにより結合を解くことができるため、大容量光伝送が実現可能となっている。
結合型マルチコアファイバと同様に、高い空間チャネル数が実現可能なマルチモードファイバと比較すると、光信号の伝搬状態の設計の自由度が高く、特に伝搬遅延ばらつきを低減可能な特長がある。これにより、風雨などの外乱による実環境の変動に追従するためのデジタル信号処理の計算量を小さくすることができ、消費電力やコストを削減した光伝送を実現することが期待できる。
これまでの結合型マルチコアファイバの研究では、主に実験室環境に置かれたファイバ素線を用いて、大洋横断級長距離伝送の実現可能性などが検証されてきました。一方、同ファイバを用いた陸上伝送システムの実用化へ向けては、時々刻々と光ファイバケーブル内の信号伝搬環境が変動するフィールド環境における安定的な大容量伝送の検証が重要だ。
こうした中、日本電信電話株式会社(以下、NTT)は、外乱によって光ファイバケーブル内の信号伝搬環境が変動するフィールド環境下において、安定した最大455テラビット毎秒の信号伝送の実証に成功したと発表した。
この実証実験では、量産化に適した既存光ファイバと同等の細さを有する12コアファイバを、伝搬遅延ばらつきを低減しながらケーブル化し、陸上フィールド環境を模擬したとう道・架空区間へ敷設した。
なお、ケーブルの大部分は、地下のとう道に敷設されているほか、0.2kmほどは地上の電柱間にケーブルを架けた空中配線区間となっており、実際の陸上フィールド敷設環境を模擬している。敷設に当たっては、商用システムと同様の構成の200心ケーブルの一部に12結合コアファイバが実装された。
この実装においては、コア間の結合状態を考慮したファイバとケーブルの設計により、伝搬遅延ばらつきとケーブル化後の曲げ特性を含めた低い伝送損失を両立しており、長距離光伝送に適した波長帯(C帯)全域を含む広い光帯域を用いた、大容量波長分割多重伝送がサポート可能だ。
そして、この陸上フィールド環境において、敷設環境における保守作業や風雨などの外乱に追従可能な大規模MIMO(多入力多出力)信号処理技術を適用することで、53.5kmの伝送距離で455テラビット毎秒の大容量伝送を実証した。
なお、今回新たに開発された結合型マルチコア融着機能を実現する住友電工によるファイバ融着技術と、安定な低損失接続を実現する千葉工大によるコネクタ技術を、フィールド検証環境内のマルチコアファイバ間直接接続に適用したとのことだ。

どちらも接続点あたりの光損失が従来のシングルモードファイバ同士の接続と同水準の低損失での接続を実現している。また、空間チャネル間の損失ばらつきも少なく、安定的な伝送に寄与した。実験では、ケーブル内の11本のファイバを折り返し接続することによって、一周53.5kmのフィールド環境周回伝送評価系を構成した。
その結果、12コアファイバフィールド光増幅中継伝送実験に成功し、安定的な大容量伝送の実現可能性を示した

さらに、日本の基幹光ネットワークの大動脈である東名阪区間をカバー可能な1,017kmの伝送距離において、大容量389テラビット毎秒の中継増幅伝送に成功した。この成果は、従来の50倍以上の伝送容量を持つ将来の陸上光伝送システムを実現する基盤技術として期待される。

今後は、関連技術分野と連携し、技術の研究開発をさらに進めることで、大容量陸上ネットワークの実用化を目指すとしている。
なお、今回の成果は、2024年9月にフランクフルトで開催された、光通信技術に関する国際会議「50th European Conference on Optical Communications(ECOC)」のセッション、ポストデッドライン論文として採択・発表された。
無料メルマガ会員に登録しませんか?
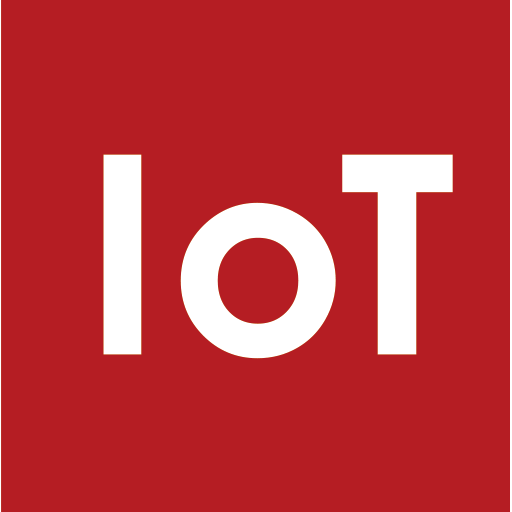
IoTに関する様々な情報を取材し、皆様にお届けいたします。