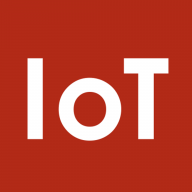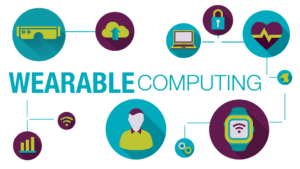量子コンピュータを実用化するためには様々な課題があるが、特に大きな問題とされているのが、計算スケールの拡大(以下、スケーラビリティ)と誤り耐性の実現だ。
一つ目のスケーラビリティの実現は、研究開発段階の小規模なシステム(~数百量子ビット)をいかにして現実問題に必要な大規模システム(数百万量子ビット~)に拡張できるかという課題に言い換えることができる。
特に外乱に弱く複雑な量子システムでは、小規模から大規模な量子計算のシステムへの発展の手法は明らかではなく、多くの物理系において実用量子コンピュータ実現のボトルネックとなっていた。
これに関して、東京大学古澤研究室の研究グループは、2019年にスケーラブルな光量子計算プラットフォームを実現した。
二つ目の、誤り耐性の実現については、現実のシステムでは必ずノイズやエラーが存在するため、エラーが生じうる環境下でも量子情報処理を正しく実行する仕組みが必要となる。その1つの方法は、誤りを検知し訂正できる「論理量子ビット」による量子情報のエンコードだ。
これについても、同研究グループでは、GKP量子ビットと呼ばれる論理量子ビットの生成に成功したことを2024年に発表している。
しかし、このGKP量子ビットの生成手法では、シュレディンガーの猫状態と呼ばれる非古典性が強い量子状態を複数用いる必要がある。
従来の光学系では、シュレディンガーの猫状態(※)の生成レートがkHzオーダーに留まっているため、この状態を複数用いるGKP量子ビットの生成レートはさらに低くなってしまう。
※シュレディンガーの猫状態:1935年にオーストリアの物理学者シュレディンガーによって提唱された有名な思考実験。シュレディンガーは量子的な重ね合わせ現象として、古典物理学ではあり得ない、生きている猫と死んでいる猫が同時に存在する状態を例示した。光学系におけるシュレディンガーの猫状態とは、位相が反転した2つのレーザ光(生きている猫と死んでいる猫に相当する)の重ね合わせ状態のことを指す。シュレディンガーの猫状態は2つのレーザ光の量子的な干渉に由来する高い非古典性を示し、この非古典性を利用した論理量子ビット生成のリソース状態としても用いられる。
こうした中、東京大学大学院工学系研究科の川﨑 彬斗大学院生及びアサバナント ワリット助教、古澤明教授らの研究チーム、マサチューセッツ大学のラジュヴィー ネハラ助教授、日本電信電話株式会社(以下、NTT)、国立研究開発法人情報通信研究機構(以下、NICT)、国立研究開発法人理化学研究所は、シュレディンガーの猫状態と呼ばれる強い量子性(非古典性)を有する光量子状態の生成レートを、従来手法より1000倍程度高速化することに成功した。
誤り耐性型光量子コンピュータを実現するためには、誤りを検知し訂正するための論理量子ビットが必要不可欠だ。直近では、光パルスを用いた論理量子ビット生成の実証実験に成功し、誤り耐性型光量子コンピュータの実現への道筋が示された。
しかし、実証実験レベルから実用レベルへ移行するためには、その論理量子ビットの生成確率を上げる必要がある。
例えば、現在広く用いられている古典コンピュータのクロックレートはギガヘルツ(GHz、1秒に10億回)の水準に達する一方で、高い非古典性を有する光量子状態の生成手法は基本的に確率的であり、その生成レートはキロヘルツ(kHz、1秒に1000回)程度に留まってた。
そこで今回の研究では、従来の状態生成・測定のための量子光源・ホモダイン測定器(HD)の代わりに、NTTが主体となり開発した非線形光学効果を用いて光を増幅する技術である「光パラメトリック増幅器(OPA)」および、東京大学とNICTが共同開発した超伝導光子検出器(トップ画)を用いることで、光源及び測定の周波数帯域を向上させた。

これにより、シュレディンガーの猫状態をメガヘルツ(MHz、1秒に100万回)の生成レートで実現した。

この方法をさらに発展させれば、ギガヘルツの生成レートの実現も見込まれ、実用レベルの生成レートを有した論理量子ビット生成の実現が期待されている。
さらに、ホモダイン測定器の前にOPAを量子的な位相敏感増幅器として用いたことで、測定系を100MHzから700倍の70GHzに高速化し、高速な光量子状態の生成を実現した。
なお、このOPAを補助的に用いた高速ホモダイン測定技術は、東京大学とNTTの研究グループが実験的に確立した新技術であり、同研究では非古典的な量子状態生成へと応用した。
下図に、生成したシュレディンガーの猫状態のWigner関数及び波束形状が示されている。この状態の生成レートは約1MHzに達しており、従来のシュレディンガーの猫状態生成と比べて3桁程度生成レートが改善されている。

現状の系ではホモダイン測定系の帯域が70GHzとなっているが、光子検出器の性能が量子状態の帯域を1GHzへとさらに制限している。もしもホモダイン測定器の帯域全体を使うことができれば、さらに70倍の高速化が見込まれている。
従来の非古典的な量子状態生成の実験では、光子検出器が最も高速かつ広帯域な素子として動作していた。一方で、今回の光源及び新規の高速な測定手法の確立によって、光子検出器の性能による帯域の制限についても、実験的な観測が可能となった。
これにより得られた新たな知見は、光子検出器のさらなる改良につながることが期待されている。
今後は、今回の高速な光量子状態の生成手法と2024年のGKP量子ビット生成の手法を組み合わせることによって、現実的な生成レートを持つ論理量子ビットの生成が可能となる。
また、従来は実証実験レベルでも生成が困難であった複雑かつ有用な量子状態の生成も現実的となり、光量子コンピュータの開発が加速することが期待されているとのことだ。
無料メルマガ会員に登録しませんか?
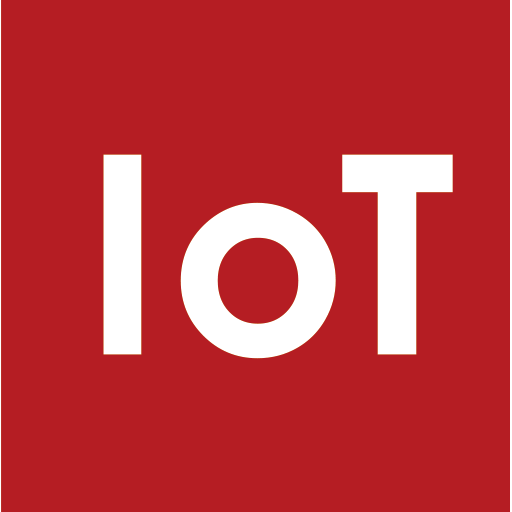
IoTに関する様々な情報を取材し、皆様にお届けいたします。