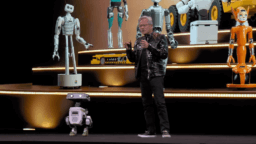特集「DX KEYWORD TEST」では、DXで必須となるキーワードに関するテストを実施。
さらに、4枚の図を使って、サクッと解説します。今回のキーワードは「KPI/KGI」。全問正解目指してがんばってください!
解説編
ここからは、DX KEYWORD TESTの設問を図解していきます。
成功を測定する指標、KPI/KGIの定義と目的

KPIとKGIは、両方ともビジネスや組織の成功を測定するための指標ですが、その定義や目的は少し違います。
ここでは、KPIとKGIの具体的な意味や違いについて紹介します。
KPIは、Key Performance Indicatorの略で、「重要業績指標」と訳されます。
つまり、定めた目標に対して、どれくらい達成しているかを測るためのプロセスや結果の指標です。
例えば、テストで良い点を取ることが目標であれば、テストへ向けて何をするべきか計画し、どれだけ勉強したかを測る指標がKPIです。
一方KGIは、Key Goal Indicatorの略で、「重要目標達成指標」と訳されます。
ゴールという単語が入っていることからもわかるように、経営における最終目標の設定や、その目標が達成されているかを計測するための指標です。
テストの例で言うと、テストの点数そのものの設定や、テストの点数を測る指標がKGIになります。
つまり、100点を取るという目標のために、どれだけ勉強したかを測る指標がKPI、実際に何点だったのかを測る指標がKGIです。
2つの関係は、KPIが達成されれば、KGIも達成される可能性が高まる関係性にある必要があります。
また、誰の立場でKGIが設定されているかをわかっておくことも重要です。
例えば、「日本の学力を向上させる」という国のKGIがあった場合、「テストで100点をとる」という先程のKGIは、KPIもしくは個人のKGIとなります。
企業の場合は、企業全体や部門、個人のKGIやKPIがあるため、どの視点からみたKGIやKPIなのかを、把握した上で活用する必要があります。
KPIとKGIを適切に設定する「SMARTの法則」

KGIは最終目標、KPIはその目標を達成するためのプロセスを考えたり評価したりすることだということがわかりました。
では、どのようにKGIやKPIを設定すればよいのでしょうか?
ここでは、ジョージ・T・ドラン博士が提唱した「SMARTの法則」という目標を立てる時に役立つ方法を活用します。
今回は、最終目標を「英語を話せるようになる」として、そのためのKPIを設定していきましょう。
ちなみに「SMART」とは、Specific(具体的)、Measurable(測定可能)、Attainable(達成可能)、Relevant(関連性)、Time-bound(期限の設定)の頭文字をとっています。
①Specific(具体的)
一つ目のポイントは、目標を明確かつ具体的に設定するということです。例えば、「もっと勉強する」という目標ではなく、「毎日英語ドリルの問題を10問解く」という具体的な行動を設定していきます。
②Measurable(測定可能)
二つ目のポイントは、測定することができるかどうかです。例えば、「英語が話せる友達と仲良くなる」という曖昧な目標より、「週に1回英語が話せる人と遊ぶ」という目標の方が、達成できたかどうかを明確に評価することができます。
③Attainable(達成可能)
三つ目のポイントは、現実的に達成できそうな目標に設定することです。例えば、全く英語が喋れない人が、「辞書1冊分の英単語を1週間で覚える」という目標は現実的ではありませんが、「1週間で英単語を50個覚える」という目標であれば、頑張れば達成することができそうです。
④Relevant(関連性)
四つ目のポイントは、目指している方向や、大事にしている価値観と関連性があるかどうかです。つまり、KGIとKPIが一貫していることが重要だということです。例えば、英語のテストで100点をとるというKGIを立てている場合、「毎日1時間、テストで100点をとった人の話を日本語で聞く」という目標よりも、「毎日1時間英会話レッスンを受ける」としたほうが、関連性が高いといえます。
⑤Time-bound(期限の設定)
五つ目のポイントは、いつまでに目標を達成するか、期限を決めることです。「毎日」「1時間」「1ヶ月で」など、期限や頻度を設定することで、目標へ向けたモチベーションを保つことができます。
今回はKPIの設定を例にあげましたが、KGIの場合も「SMARTの法則」は有効だとされています。
英語を話せるようになりたい人の場合、「英語を話せるようになる」ではなく、「1年間でTOFLE 80点をとる」など、SMARTなKGIを設定する必要があることがわかりましたね。
KPIとKGIの測定方法

ここまでは、KPIとKGIの概要を理解するうえで、個人の目標達成を例に挙げてきました。
個人の目標であれば、KPIやKGIをどれだけ達成できたかを測定したり評価したりすることは簡単ですが、組織単位でKPIやKGIを測定するにはどうしたらいいでしょうか。
組織の場合には、それぞれの部門や部署、個人のKPIを評価するために、日々のデータを収集することが必要不可欠になります。
例えば、スーパーやコンビニを経営している小売企業が、1年間の売上高1000億円達成するというKGIを立てたとします。
売り上げ1000億円を達成するためのKPIは、部署や店舗、個人で設定されるため、日々の取り組みや売り上げのデータを収集して、蓄積する必要があります。
蓄積されたデータは毎月や四半期ごとなど、定期的に達成度を測定します。
順調にKPIやKGIが達成されていなければ、問題点や改善点を明らかにして、KPIの練り直しが必要となるでしょう。
例えば、KGIを達成するためのKPIとして、「平均客単価の向上」を立て、商品バリエーションの拡充やセール品の販売、セット販売の導入などの施策を実行したとします。
施策を実行してある程度たったら、どの商品がどれだけ売れたのかといった店舗の販売データや、どのような顧客が買っていってくれたのかといった顧客データなどを収集して分析します。
結果として平均客単価が設定した金額に到達していなければ、実施する施策やKPIを見直していきます。
そして、KPIが達成されることで、どれだけKGIに影響があったのかもモニンタリングする必要があります。
人時生産性を向上させKGIを達成したサイゼリヤの事例

ここでは、KGIとKPIの事例として、公益財団法人が2014年に発表している企業分析レポートを参考に、サイゼリヤの事例を紹介します。
株式会社サイゼリヤは、イタリアンレストラン「サイゼリヤ」をチェーン展開しているフードサービス事業者です。
サイゼリヤのKGIは、ローコストオペレーションと顧客に喜ばれる料理の提供で、各店舗の売上を向上させることでした。
そして、このKGIを達成するために、従業員1人が1時間で生み出す粗利益である、「人時生産性」を高めることをKPIに設定しました。
具体的には、これまで1時間かかっていた掃除時間を、30分に短縮させるといったことや、調理作業を単純化させることで、1人のスタッフがフロアでもキッチンでも働ける環境を整備するなどの施策を実施しました。
また、同時に多くの調理を行える厨房設備を開発して導入したり、食器の汚れを効率よく落とすために洗剤を変えたり、スプーンの表面処理を変えたりするなど、従業員が扱う設備の改善も行いました。
これにより、人時生産性は、業界標準の1時間あたり3000円を上回り、1時間あたり4000円前後の生産性水準を達成しました。
人時生産性を向上させたことで、コスト削減することができ、顧客にはコストパフォーマンスの高い価格設定で料理を提供することができました。
その結果どの程度各店舗の売上が向上したかは明示されていませんでしたが、サイゼリヤはその後、人時生産性を1時間あたり6000円まで高めることを目標にしました。
この事例から、設定したKPIがKGIに良い影響を与えていたことが伺えます。
無料メルマガ会員に登録しませんか?

IoTに関する様々な情報を取材し、皆様にお届けいたします。