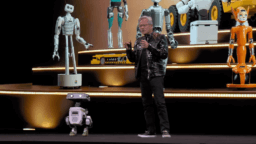外部からデータを取得しなければならない理由
小泉: 次にデータの売買の話に移っていきたいと思います。ただやはり、さきほどの歩留まりの改善にデータを活用するという話から、データの売買に話を進めるというのは飛躍があるように思うんですね。
データを売買したり、データを使って新たなサービスをつくったりとなると、もう少し緻密なデータや広範囲なデータがないと難しいと感じますが、どうでしょうか。
八子: たとえば小売・流通の店舗でデータを取る場合に、その目的が「お客さんの顔を認識する」ことだけであれば、ものすごくピンポイントの領域のデータでしかないわけです。
そこに、POSシステムに蓄積された「何の商品がどれだけ売れたのか」といったデータやお客様の動線のデータなどを集め、店舗の状態をすべて可視化しようとすると、データは膨大になります。
そこで初めて、天気のデータや食材の仕入れに関連するデータが足りない、といった「データの不足」に気づくのです。その場合には、データを外部から取ってこないと高度な分析はできません。また、大量のデータを自社だけで蓄積していると、ストレージコストの負担も大きくなります。
そこでようやく、データ連携の環境にアクセスしたりAPI連携したりといった具体的な話が始まります。ですから、まずは自社である程度のデータがたまっていない限りは、そこまでいかないでしょう。
小泉: なるほど。製造業だと、ある産業機械メーカーがタイとロシアに機械を売っているとします。この二つの国は気温がまったく違いますから、それぞれの気温のデータを集めることで、機械の故障に対する気温の影響を分析し、自社の製品を改善していくことができますよね。
もうちょっと高温帯に耐えられる部品を使わないといけないなとか、寒いところでも動くような設計にしないといけないということがわかります。それはイメージつきますね。

八子: ウフルでご相談頂いている案件の中に、海の近くと山の近くでは、潮にさらされている影響で、設備の故障状況が違うという事例もあります。あるいは、同じエリアでも粉塵の発生の度合いで加工精度が変わることもあります。
小売であれば、鮮度を管理してお店に並べるわけですが、特にチルド品(0℃前後で輸送、販売する食品)の場合には、きちんと温度が管理されているかの証拠提出を義務付ける「コールドチェーン・マネジメント」の制度化も米国を中心に始まりつつあります。そうすると、自分たちでは結局、データが取れないのです。
小泉: 小売・流通のサプライチェーンは特にそうですよね。製造過程・倉庫での在庫時・トラックの中・店頭といったそれぞれのデータがなければなりません。
高級なワインなどは昔から緻密にやってきたのでしょう。高級なワインを扱うお店では、その保存状態をさかのぼって聞いて回ったうえで仕入れるようですからね。開けてみないとわからないというワインはダメで、初めから品質が保証されていなければならないのです。
そういうことが、日常生活に関係のある製品でもひろがっていくということですね。冷凍品でも、「これは一回溶けたんじゃないか?」というような氷の塊があったりしますからね。
八子: そうです。ある企業さんで、全体の3分の1の製品は既定の温度から外れているというデータを我々も目の当たりにしています。そこはやはり、複数のプレイヤーでひとまとめに分析や管理をするという体系的なしくみが必要になるでしょう。そうなったらようやく、データが流通していく段階に移るのかなと思います。
無料メルマガ会員に登録しませんか?

技術・科学系ライター。修士(応用化学)。石油メーカー勤務を経て、2017年よりライターとして活動。科学雑誌などにも寄稿している。