株式会社ソラコムが主催する日本最大級のIoTカンファレンス「SORACOM Discovery 2019」が7月2日、グランドプリンスホテル新高輪(国際館パミール)で開催された。本稿では、その中で行われたセッションの一つ、「基調講演パネルディスカッション:製造業を超えて ~超現場主義の製造業IoTから始まる変革~」の内容について紹介する。
登壇者は、旭鉄工株式会社代表取締役社長/i Smart Technologies株式会社の木村哲也氏、株式会社田中衡機工業所 代表取締役社長 田中康之氏、フジテック株式会社 常務執行役員 デジタルイノベーション本部長 友岡賢二氏の3名。そして、モデレーターは、株式会社ウフル CIO(チーフ・イノベーション・オフィサー)兼IoTイノベーションセンター所長 エグゼクティブコンサルタントで、株式会社アールジーン(IoTNEWSの運営母体)の社外取締役でもある八子知礼氏がつとめた。
課題は「現場」にあり
今回登壇した旭鉄工・田中衡機工業所・フジテックの3社とも、「ものづくり」を行う企業でありながら、IoTの活用に先駆的に取り組んできた企業だ。ものづくりとIoTはどのように結びつき、効果をもたらすのか。そのカギは、「現場」の課題にあるようだ。
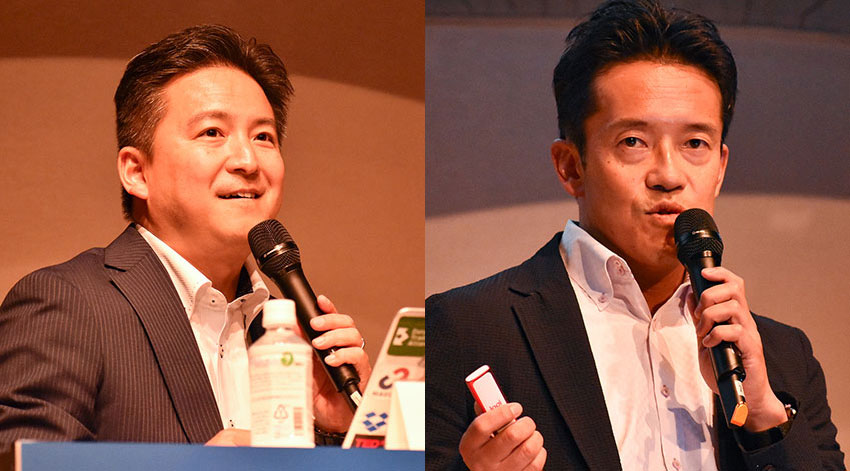
旭鉄工は、愛知県碧南市に本社をかまえる、自動車部品のメーカーだ。2014年から工場の「カイゼン」(生産性の改善)活動にIoTを積極活用し、自社で成果を見出してきた。そして、自社の現場で育て、成果を実証したソリューションを製品として他社に販売するため、2016年に「i Smart Technologies」(以下、iSTC)という別会社を設立した。
カイゼンにIoTを活用したきっかけは何だったのだろうか。木村氏は次のように語った。
「カイゼン活動で最も大変なプロセスは現状把握だ。現場では、従業員が紙と鉛筆、電卓を使って生産状況を管理していることが多い。昭和のような話だが、これが実情だ。こうした現状把握は24時間365日、機械に任せればよい。その分、従業員は現状把握から見つかった問題を解決するという、『付加価値の高い仕事』(人間にしかできない仕事)に時間を使うことができる」
iSTCが手がけるメインのソリューションは、設備の稼働状況をモニタリングするIoTシステム。古い設備でも、センサーを後付けすれば、無線通信によってクラウドにデータが蓄積され、稼働状況の「見える化」が可能だ。自社の検証では、2015年に6ライン、2018年には41ラインの生産性を改善した(各ライン30%以上の改善)。
一方、iSTCのソリューションを導入した顧客は180社以上。そこでの効果については、使用して5か月が経過している顧客のデータを総計すると、平均1.25倍(47%→59%)の生産性の改善が確認されている。「私はよくお客様に、御社の設備の稼働率がどれくらい知っていますかと質問する。大抵誰もが80%くらいと答える。しかし実際は40~50%だ。また高かったとしても、人が記録しているのでデータは正確ではないことが多い」(木村氏)
他にもiSTCでは、ソラコムの「LTE-Mボタン」やAIスピーカーを使って、ラインの停止理由を記録するソリューションなど、カイゼンのツール拡大をはかっている(iSTC木村氏へのインタビュー記事はこちら)。
次ページ:深刻な人材不足をIoTで解決
無料メルマガ会員に登録しませんか?

技術・科学系ライター。修士(応用化学)。石油メーカー勤務を経て、2017年よりライターとして活動。科学雑誌などにも寄稿している。




















