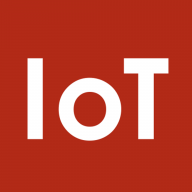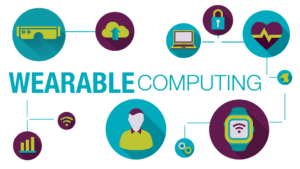ドライアイは、眼科を受診する原因の上位を占めており、特に日本では、6人に1人の割合でドライアイが発症すると報告されている。
眼科領域においては、特に網膜疾患や視神経疾患(眼底疾患)のスクリーニングや診断において、AIの活用に注目が集まっているが、診断やAI開発のための機械学習に必要な、画一的で、大量の細隙灯顕微鏡の画像データを取得することが困難であるため、AI開発が進んでいないのが実情だ。
そうした中、OUI Inc.の研究グループは、アジアのドライアイ診断基準に重要な涙液層破壊時間(TFBUT; tear breakup time)を自動で推定するアルゴリズムを用い、ドライアイAI診断モデルを開発した。
研究グループはまず、スマートフォンアタッチメント型細隙灯顕微鏡であるSmart Eye Camera(以下、SEC)を開発し、医療機器として実用化をした。
そして、このSECを用いて、大量の細隙灯顕微鏡の画像データを取得することで、ドライアイ診断AIの開発を行った。
具体的には、SECを用いて収集された、後向きの79症例158眼分の前眼部動画すべてを静止画に分割することで、合計22,172枚の画像に分割した。
次に、診断に不適切な5,732枚の画像を除外し、残りの16,440枚に対し、眼科専門医がTFBUTに関わる層破壊(break up)の所見を、アノテーション(タグ付け)し、 12,011枚の学習用データセット、1,599枚の評価様データセットに分類し、すべての学習用データセットを機械学習にかけた。

学習用データセットを使用して開発したドライアイAI診断モデルは、眼科専門医のドライアイ診断に対して、感度0.778、特異度0.857、機械学習の評価指標であるAUC0.813を達成した。
また、Gradient-weighted class activation mapping(GradCAM)を用いた、ヒートマップによる可視化技術でも、AIは正確にTFBUTの所見を捉えていることが確認された。(トップ画参照)
この結果により、今回開発されたアルゴリズムは、特筆すべき高い診断感度や特異度は達成できなかったが、従来であれば万を超える多数の症例を収集しないと開発不可能であった、画像診断アルゴリズムを79症例で達成したことができた。
今後は、収集する症例数を増やし、アルゴリズムを最適化することで、より精度の高いドライアイAI診断モデルを開発し、プログラム医療機器(SaMD)としての実用化を進めていくとしている。
なお、今回の研究は、国立研究開発法人日本医療研究開発機構、日立財団、近藤記念財団、ユースタイルラボ、興和生命科学振興財団、大和証券ヘルス財団、H.U.グループ中央研究所、慶應義塾大学 グローバルリサーチインスティテュート等の研究助成で行われた。
また、研究の成果は、日本時間の2023年4月10日に米国科学誌「Scientific Reports」に公開され、慶應義塾大学医学部確認のもと、本日日本で初めて情報解禁がされた。
無料メルマガ会員に登録しませんか?
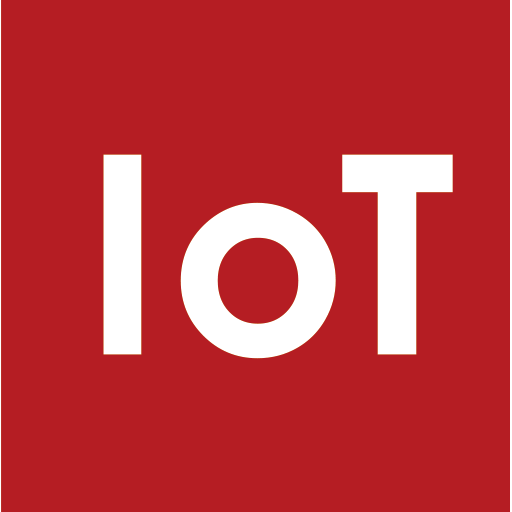
IoTに関する様々な情報を取材し、皆様にお届けいたします。