業界単位のシェアドサービスセンターが必要
八子:倉庫において、物理的なロケーションや、持っているアセット、トラッキングするべき商品などの管理体系がまだ整備されていない、という印象を受けます。
秋葉:おっしゃる通りです。倉庫は様々なお客様の荷物を預かるわけですが、倉庫にモノが入ってきた時点で統一的に管理出来ればよいのです。しかし管理のためには、荷物に対してバーコードやRFIDをつける必要があるわけですが、その費用は、だれも払ってくれないわけです。
八子:その問題は解消することが難しいことなのでしょうか。
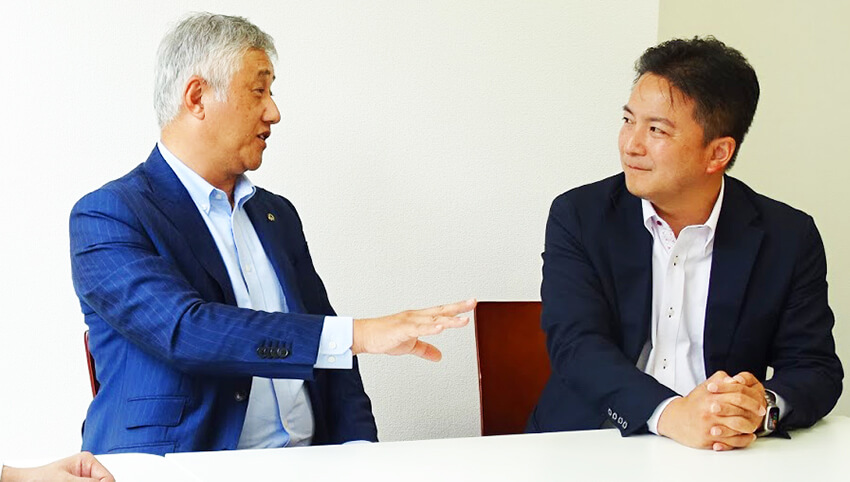
秋葉:結局、物流費用、つまりモノを運ぶ費用としていくら払うか、という発想からスタートしているので、倉庫側が「統一するためにバーコードやRFIDを導入したい」といっても、「それは物流の品質を上げるためだから、倉庫側で費用を持ってください」と言われてしまいます。
小泉:各業界は物流が抱える問題については十分に認識しているはずなのに、それでもお金は出してくれない、という感じなのでしょうか。
秋葉:それぞれの予算が決まっており、場合によっては上から「物流のコストを抑えられないのか」と言われるところもあるので難しいと思います。
八子:そうなると業界単位でシェアドサービスセンターのような施設を作り、共通のタグを使用してみんなでやります、それに物流側も出資します、といった施策を考えざるを得ないですよね。
秋葉:それは良い案です。人手不足になるよね、という話を各業界でこれだけ議論しているわけだから、みんな少しずつコスト負担して全体で取り組まないと物流の問題は解決しないと思います。
テクノロジーを共有するための団体が無い
小泉:現場で起きていることは世の中に認識されているけれど、結局誰も取り組まない、というのはどの業界でもよく見かける光景ではあります。
秋葉:結局「だれが何をどれだけ負担して、それぞれにどういうメリットがあるのか」という事を明確にしなければいけないと思います。例えばデータのオープン化の話にしても、データを持っていない側にとってはメリットが大きいけれど、提供する側にとってはメリットが無い場合が多い。このバランスをどうするのかという問題があります。
八子:データを出す側が「このデータを使っていいよ。ただしある程度、中立性のある団体に運用してもらって、そこが使った分のあがりはこちらがもらうよ」という形にせざるを得ないですよね。
秋葉:データを出した側にそうしたメリットがあるしくみをきちんと作るべきですよね。
小泉:そういうことを統括する団体というのは、ロジスティクス業界にはないのですか。
秋葉:労働集約や既得権の話をする団体はありますが、データやテクノロジーを調達し、それを貸し出す仕組みを持った団体は全くありません。
小泉:やれることは分かっているのに、実行できる環境が整っていないのは厳しい状況にありますね。
次ページは、「プラットフォームの乱立と集約」
無料メルマガ会員に登録しませんか?

1986年千葉県生まれ。出版関連会社勤務の後、フリーランスのライターを経て「IoTNEWS」編集部所属。現在、デジタルをビジネスに取り込むことで生まれる価値について研究中。IoTに関する様々な情報を取材し、皆様にお届けいたします。




















