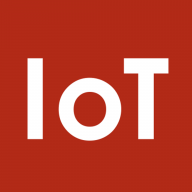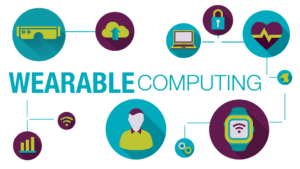2021年12月10日に開催された「Conference X in 東京」のレポート第2弾は、セッション2「DX-ESG/CNストラテジー・チェンジ」〜ESG経営のためのDX、環境の可視化、ESGスコア対応〜、の内容について紹介する。
- インクルージョンジャパン株式会社 代表取締役 服部結花氏
- 日本オラクル株式会社 バイスプレジデント事業戦略統括 首藤聡一郎氏
- 株式会社ゼロボード 代表取締役 渡慶次道隆氏
- 株式会社INDUSTRIAL-X 取締役 吉川剛史氏(モデレータ)
ESG投資が高まる世界の流れ
まず、環境(Environment)・社会(Social)・ガバナンス(Governance)要素に考慮した投資活動である、ESG投資の現状について、ESG投資を行うベンチャー企業の代表を務める服部氏は、年々盛り上がりをみせていると説明する。
ひとつはESG投資残高の伸び率だ。2016年は22.8兆ドル、2018年は30.7兆ドル、2020年は35.3兆ドルと、年々増加しており、運用総資産に占めるESG投資残高割合は35.9%と、4割弱にのぼる。

また、2021年10月から11月にかけて行われた気候変動に関する国際会議であるCOP26では、「ネットゼロのためのグラスゴー金融同盟」が立ち上がった。
この同盟では、今後30年にわたり、100兆円がカーボンニュートラル達成に向けた支援に充てられるとされており、ESG投資への流れは加速している。
こうした流れに対し服部氏は、「環境に配慮した流れという意味で、ポジティブに捉えられる部分がある一方、裏を返せばESGに配慮をしない企業にはお金が流れないということを意味している。特に時価総額5,000億以上の企業はすでに機関投資家から強い圧がかかっている。」と語る。

上図は、企業がESGに関するチェックリストと統合報告書を格付け機関に提出することにより格付けが行われ、その格付け結果をもとに投資家は融資先を決めるという流れを表している。
つまり、これまでは財務情報をIRとして株主や投資家に開示されていたが、今後は非財務情報を統合報告書として開示する必要がでてくるということだ。
統合報告書を見て、様々な格付け機関が格付けをし、格付けを基に機関投資家が出資を行うかどうかを決定する、という上図の流れは、すでにできていると服部氏は述べる。
対応の遅れを取る日本の現状
これに対し吉川氏は、「こうした流れに対して海外の企業がシビアな対応を始めているのに対し、日本企業の対応は遅れとっている印象を受ける。」と指摘する。
アメリカに本社を置き、非財務情報レポートなども積極的に開示を行っているオラクルの首藤氏は、その原因のひとつとして、法律の強制力を挙げた。
欧州委員会では、環境や社会的課題、ガバナンスなどの非財務情報の開示に関する指令として、開示義務の対象となる企業の拡大を示す「企業持続可能性開示指令案」を2021年4月に発表している。
また、米国では、製品製造の際、紛争鉱物を使用していないことを確認するための「ドッド・フランク法」があり、鉱物のサプライチェーンを開示する必要がある。
そうした流れの中から、国を上げて追跡や監査が行われ、適さない企業は株価の下落や取引先の減少というリスクが隣り合わせのため、企業はESGに取り組まざるをえない状況が生まれているのだという。
また、前職で金融業界に従事しており、現在国際的なアナリスト協会に属しているという渡慶次氏は、様々なESG評価機関が提示するESGスコアに対し、日本企業がまだ貪欲な姿勢ではないことを指摘する。
「欧米の企業は、ESGスコアのスコアリング会社が評価した結果に対して、どうしてこのようなスコアなのか、どう改善し、経営戦略に落とし込んでいくべきなのか、スコアが上がる方法をスコアリング会社に聞く。しかし日本の企業はスコアリング会社との会話が極端に少ない。」と述べた。
さらに服部氏も、「ESGのルール作りは、格付け機関も企業も取り組み始めたばかりで、現状は過渡期。たくさんの小委員会が立ち上がり、ルール作りをしている最中だが、世界の主要なプレーヤーの小委員会への日本企業の参画は1社のみ。」と、日本企業の消極性を問題視した。
CO2削減はサプライチェーン全体の問題
次に、CO2排出量を算定報告するための国際基準「GHGプロトコル」における、サプライチェーン全体のCO2排出量を把握するための「Scope」(以下、スコープ)について、渡慶次氏より説明があった。
スコープは、CO2が排出される範囲を表すため、スコープ1、スコープ2、スコープ3という分類に分かれている。
スコープ1は自社で使われたエネルギーから排出される直接排出量、スコープ2は他社から供給された電気などのエネルギーを活用した際に排出される間接排出量を指す。
そしてスコープ3は、15のカテゴリーからなる、調達関係の上流から、出荷以降の下流に至るまで、スコープ1、2以外の全ての間接排出量を指す。

スコープ3の15の分類の中には「投資」というカテゴリーがあるため、金融機関自体もCO2を削減しなければならないことを示しており、融資先に対してCO2を下げるよう指摘が行われる。
また、メーカーは自社のスコープ3を下げるために、仕入れ先の企業や配送に関わる企業などの関連会社に対してCO2に関する追跡を行い、下げるように求めるという流れが生まれる。
こうした流れに対し渡慶次氏は、「CO2の削減が実行できない企業がサプライチェーンから締め出されてしまう可能性がある。」と警告を鳴らした。
また、吉川氏は、中国では、新エネルギー車をはじめとするEV車の生産・開発が基準を下回ると、基準を上まった企業に対して「クレジットを買い取る」という形で対価を支払わなければならない制度を導入している事例を取り上げ、「クレジット収入が入った企業はさらに商品の値下げなどを行ってくれば、二重で価格競争が厳しくなる。」と、取り組まない企業に対する危機感を話した。
CO2排出量を可視化し、企業価値を訴求する
続いて渡慶次氏より、こうした差し迫った状況に対して、企業はどのような取り組みを行なっていけばいいのか、セロボードのソリューションを活用した具体的な施策について語られた。
ゼロボードは、CO2排出量算出クラウドサービス「zeroboard」という、企業のCO2排出量を算出し、可視化を行うサービスを展開している。そうしたCO2排出量の情報を、国や金融庁、仕入れ先や消費者に開示をし、企業価値を訴求するというものだ。

「GHGプロトコル」では、サプライチェーン全体でのCO2削減が求められているため、上場か非上場かといった、企業の規模の大きさに関わらずCO2削減に取り組む必要がある。
渡慶次氏は、非上場企業であってもこうした情報開示を活用するべきだとし、その理由のひとつとして、「先ほど述べたように、金融機関も融資先のCO2の排出量を下げたいと思っているため、CO2を下げた企業に対しては利息を減らすといった「グリーンローン」や「サステナビリティ・ローン」という制度を導入しているからだ。」と、開示することのメリットを述べた。
また、COP26で発表された、バリューチェーン全体での製品レベルの炭素排出量データの計算と交換に関するガイダンスである「PathfinderFramework」では、プロジェクトごとのカーボンフットプリントをどう評価し、開示するかといった指針が示されている。

商品ごとのCO2排出量を計算してくことで、スコープ3として受け取った会社が、スコープ1と2を追加して、次の会社へと渡していくことができるというものだ。
こうした指針からも、サプライチェーン全体で取り組んでいくべき課題だということが分かる。
各企業が自分ごととし、取り組む必要性
服部氏からは、各業界が、具体的にどのような取り組みを行なっていけばいいのかについて、参考になる指標として、MSCIという格付け機関が発表している「ESG Industry Materiality Map」が紹介された。

これは、業界を選択すると、環境(Environment)、社会(Social)、ガバナンス(Governance)のセクターごとに、具体的に何%、どの項目に取り組むべきかが示されるというものだ。
吉川氏は、「こうした指標があると、重要度や優先順位が分かり、アクションが取りやすくなる。」と、積極的な活用を促した。
一方渡慶次氏は、サプライヤーがCO2排出量のデータを開示してくれない可能性を指摘した。
「現状ではデータが十分でないため、調達した材料や購入したサービスは、国などが発表している評価値を活用して評価をしている。しかし今後は、各企業が自社で収集したデータ、実績値をどれだけ集めておけるかが重要なポイントになってくる」と語る。
「現段階では、海外も含め標準値での評価にとどまっているが、すでに業界ごとのメーカー主導で、どのようにデータを受け渡していくか、というサプライヤーを巻き込んだ話は進んでいる。」と、今のうちから手を打っておく必要性を述べた。
ESG経営に取り組む先行事例
ESGに関するデータを集め、開示する必要があることは分かったが、結果が良くないと開示をしたくないという気持ちが働きがちだ。しかしすでにESG経営に取り組んでいる企業であっても、必ずしも良い結果だけを開示しているわけではないという。
その例として、服部氏は、食品や飲料を扱うネスレ社の発表を挙げた。
ネスレは、健康食品度格付(ヘルス・スター・レーティング、HSR)において、自社の主要食品と飲料の60%以上が基準を満たしていなかったことを発表している。
これに対しメディアや消費者からは一部避難を受けているが、グローバルな格付け機関の視点ではポジティブに捉えられているという。
実際に、オランダNGO栄養アクセス財団(ATNF)が発表した、食品大手の栄養に関する経営レベルランキング「栄養アクセス・インデックス(Access to Nutrition Index:ATNI)」では、ネスレが1位となっている。

その理由として服部氏は、「まずはデータがある、という状態が望ましい。結果が必ずしも良くなかったとしても、これから改善するための意志と材料があると判断された。」と語った。
また、世界の先行事例として、ユニリーバとの取り組みを首藤氏が語った。
オラクルはユニリーバの物流や積載の荷物の最適化といった、効率化を図ることでトラックの台数を減らし、CO2削減に貢献している。
首藤氏は、「ユニリーバはこうした取り組みをきっかけとして、経営層が新しいブランド作りの一環にしており、ESG経営企業というアピールを行っている。ESGに関し、「CO2削減」という部分的な側面を見るのではなく、経営の在り方と捉えて発信している。実際にユニリーバの株価は競合企業に比べ良い。」と述べた。
多角的な視点で経営をトランスフォームしていく
そして吉川氏は、今後、ESGとDXの流れがどのようになっていくのかを3者に聞いた。
首藤氏は、「ESG経営を含め、人手不足やグローバル対応など、日本の企業はやらなければならないことがどんどん増えていく。そうした中で、やれる体力がないと感じる企業もいると思うが、ここで余剰の経営資源を生み出しておく必要がある。」とし、今後息切れしないための準備を促した。
「まずは既存の業務やオペレーション、ビジネスプロセスなどで、省人化や自動化できる部分は取り組んでいく。そうした余剰の経営資源を生み出すためのデジタル活用や、コスト構造の変革を根本的に考えて実行していくことが求められている。」と、ESG経営を実行するためにも、デジタルを活用してトランスフォームしていくことの重要性を語った。
服部氏は、「2022年は仕込みの年になる。そのために目標からバックキャストし、何をいつまでにすべきか、具体的なデータと数字で目標づくりをしていくことが重要。」と、2023年に求められるであろう具体的な対応に向けて、2022年は足場を固める必要があるとした。
また、「目標が明確になれば、自社だけでは無理だということに気づく。そこでバリューチェーンの企業や、ベンチャー企業などとうまく組んで基盤ができている企業は、大きな差をつけることができる。」と、適切なエコシステムづくりの強化を訴えた。
渡慶次氏は、「車の運転で言うと、PLやBL、CO2排出量などは過去の数字であり、バックミラーに映っている風景のようなもの。一番重要なのはフロントガラスに映る景色。今後どの道をどのように進むのかを統合報告書に書き込まないと意味がない。ルールができると、まず外形的なものから着手されがちだが、企業の経営、文化、目的を示す必要がある。」と、統合報告書の在り方自体に新たな視点を加えた。
さらに、「2025年以降になるとカーボンプライシングや炭素税といった仕組みが導入され始め、確実に取り組まざるを得なくなる。そうなる前に、今のうちからCO2排出量を可視化し、各ポジションで行える取り組みを周りにも理解してもらうことで、企業価値が高まり、新たな価値創造をおこなうことができる。」と、各ステークホルダーが情報共有を行うことで目標達成を実現することができ、新たな価値創造にもつながると語った。
無料メルマガ会員に登録しませんか?

現在、デジタルをビジネスに取り込むことで生まれる価値について研究中。IoTに関する様々な情報を取材し、皆様にお届けいたします。