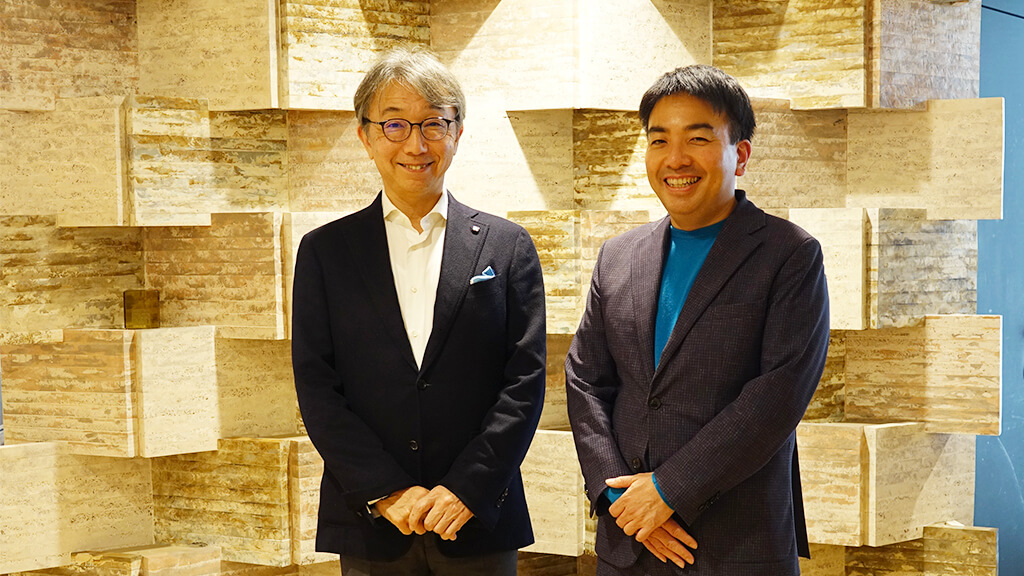株式会社船場(以下、船場)は、商業施設やオフィスをはじめ、様々な空間において、企画・設計・施工・メンテナンスをトータルでサポートしている。
また、サプライチェーン全体でより良い社会の共創を目指すことをテーマに、「エシカルデザイン」を推進している企業でもある。
2021年4月に全面リニューアルを完了した自社オフィスでは、リニューアル前のオフィスで使用していた資源のリユース・リサイクルに加え、現場工事で排出された廃材などを活用し、新たに家具やアートなどへと生まれ変わらせている。

そうした中、船場は、株式会社ウフル(以下、ウフル)の支援のもと、カーボンフットプリント(温室効果ガスをCO₂に換算した値)を算出する「Salesforce Net Zero Cloud」(※)を導入し、脱炭素への取り組みも推進している。
そこで本稿では、船場がエシカルな活動を始めたきっかけや「Salesforce Net Zero Cloud」導入した経緯、今後の展望などについて、株式会社船場 代表取締役社長 八嶋大輔氏と、株式会社ウフル 代表取締役社長CEO 園田崇史氏にお話を伺った(聞き手:IoTNEWS 小泉耕二)
※「Salesforce Net Zero Cloud」:企業の環境データを収集・分析し、温室効果ガスの排出量と吸収量を差し引きゼロにする「ネットゼロ」実現に必要な情報をダッシュボードで可視化する製品。温室効果ガスの排出量の算定と報告の国際基準であるGHGプロトコルに基づき、事業者による温室効果ガス排出量の算定・報告対象範囲の区分であるScope 1〜3を算出する。
他社間連携必須である「ネットゼロ」の成功モデルとなるために
IoTNEWS 小泉耕二(以下、小泉): 船場は、エシカルなオフィスづくりをはじめ、脱炭素へ向けた「Salesforce Net Zero Cloud」の導入など、積極的な環境保全や社会貢献に取り組まれていますが、こうした取り組みに注力しようと思われたきっかけは何だったのでしょうか。
船場 八嶋大輔氏(以下、八嶋): 私は船場に入る以前、30年ほどファッションビジネスに携わっていました。
アパレル業界やファッション業界では、何が売れるのか的確に予測することはできないため、多めに生産しておくのが常識でした。コストの何倍かで販売できれば、廃棄分があったとしても利益は出るようになっています。
しかし、企画・製造から輸送、販売・廃棄に至るまでのサプライチェーンは長く、その工程中には大量の水の使用や水質汚染、CO₂の排出や大量廃棄など、環境に与える影響が大きいという課題がありました。
当時海外の大手ブランドを担当していた時に、大量廃棄していることを、SNSを中心にメディアで叩かれたという経験もあります。
また、船場に就任してからも、同様の課題が見えてきました。インテリアや内装業界からすると、ファッション業界は顧客です。シーズンごとのコンセプトに合わせた内装に変えるのですが、家賃が高い立地の場合が多く、改装は少しでも早く終わらせたいというニーズがあります。
そのため、まだ使える設備もリサイクルに回す時間がなく、混合廃棄物として廃棄せざるを得ません。そして、このような課題はファッション業界に限らず同様にあるのが実情です。
この産業構造に疑問を抱き、貢献できないかという想いに共感してくれた社員や企業と共に、サステナビリティを考慮したオフィスの引越しをしたことがきっかけです。
小泉: そうした課題意識から、エシカルな取り組みを積極的に行っていたのですね。一方、「Salesforce Net Zero Cloud」を活用した脱炭素の活動とは直接関係がないように感じるのですが、どのようなきっかけで導入に至ったのでしょうか。
八嶋: 世の中の流れとして、パリ協定で定められたCO₂削減目標である「SBT(Science Based Targets)」や、温室効果ガスの排出量を算定・報告する際の国際基準「GHGプロトコル」が策定されるなど、環境問題における基準が出始めています。

弊社でも独自のエシカル活動に加え、この基準に準じた企業活動も行ってきました。GHGプロトコルのスコープ1や2は、自社エネルギーや他社供給エネルギーの排出量を算出する範囲ですので、自社内で取り組むことができました。しかし、調達から出荷以降までのエネルギー排出量を算出する必要があるスコープ3では、サプライヤーとの連携が不可欠です。
そうした中、「Salesforce」を通じてウフルと知り合う機会があり、「Salesforce Net Zero Cloud」導入へと至りました。
ウフル 園田崇史氏(以下、園田): 船場は弊社同様「Salesforce」のトレイルブレイザー(「Salesforce」を活用してDXを推進する先駆企業)であり、Salesforceコミュニティの重要な存在です。
ネットゼロを実現するためには、八嶋さんがおっしゃる通り、自社のデータだけでなく、サプライヤーのデータも取得する必要があるため、連携する必要があります。
そうした意味で、顧客やパートナー企業、社内のコミュニティを含め大切にされている船場であるからこそ、成功モデルに成りうると考えています。
また、エシカルな活動の軌跡や重要性が実感できる自社オフィスをはじめ、目にすることができる具体的なアクションを取られている船場は、ネットゼロの成功体験を共に作り上げていくベストな企業だと感じています。
脱炭素への取り組みを可視化することで生まれる新たな価値
小泉: これから「Salesforce Net Zero Cloud」を活用しながらスコープ3に取り組むということですが、具体的にはどのようなことを実施していくのでしょうか。
八嶋: まずは、廃棄に関するCO₂排出量の可視化や、削減に取り組んでいきたいと思っています。
廃棄物何トンあたりどれだけのCO₂が排出されるかという規定された計算式はあるのですが、弊社が取引をしている廃棄物処理業者は、その計算式では算出されないリサイクルなどの企業努力により、CO₂削減をしています。
このような企業努力を加味した上で可視化すれば、CO₂削減にどれだけ貢献しているのか、適正に理解してもらうことができ、廃棄物処理業者のPRにもなります。さらに、リサイクルをすることでその売価が廃棄物処理業者の売り上げになるため、新たなビジネスモデルとなりつつあります。
サステナビリティを考えながら経営をしている廃棄物処理業者はまだまだ少ないのが現状ですが、CO₂削減するための企業努力をすることで、会社の価値を上げ、新たなビジネスを生むことができれば、脱炭素へ向けた活動を行う仲間が増えていくと考え取り組んでいます。
園田: 日本は内需が減っていく中、いかに付加価値をつけて単価をあげていくかが大事なポイントです。
付加価値の形は色々とあると思いますが、ネットゼロは大きなテーマのひとつです。ネットゼロに取り組むということは、エシカルであると同時に、ビジネスを成功させるためにも大きな要素なのです。
そうした中、現状を正しく把握していない状態で計算式通りに算出しているため、実際の数値よりも高い排出量を報告しているという例がよくあります。
まずは現状を正しく可視化し、正しい排出量を算出する。その上で改善できる箇所がどこかを見極めていくことが重要です。

特に内装・建築業界は無駄の多い業界ですが、その分無駄が減ることで、世の中を変える力があると考えています。
小泉: サステナブルな事業者であることを可視化できれば、そうした内装業者や廃棄物処理業者を活用する企業にとっても良いPRになりますし、良い循環が生まれるイメージが湧きました。
試行錯誤しながら、先駆けて脱炭素へ取り組む意義とは
小泉: 「Salesforce Net Zero Cloud」における、今後の展望について教えてください。
園田: 「Salesforce Net Zero Cloud」については、必要に応じた機能拡張を行っていきたいです。既に、日本独自の地球温暖化への対策を取り決めている「温対法」に準じたサービスを、追加オプションとしてモジュール化するなどの機能補完を行っています。
また、将来的にはサプライヤー間をつなげていく仕組みも構築していきたいと考えており、「Salesforce Net Zero Cloud」は適したソリューションであると自負しています。
「Salesforce」自体がグローバルに普及しているサービスであり、利用者数も多いことから、多くの人が慣れ親しんだUI・UXを実現しているからです。
導入しやすいという点は普及に大きく寄与し、今後サプライヤー間をつなげていく仕組みを構築した場合においても、問題なく利用することができると考えています。
小泉: 導入しやすく、グローバルなプラットフォームであるということは、普及拡大に必須な項目ですね。
それでは最後に、エシカルな取り組みを行っていこうと考えている企業に対してメッセージをお願いします。
八嶋: まずは、直感的に「おかしい」と思うことが大切です。例えば建築業界では、利用される資材はほとんどが輸入材です。日本は森に囲まれた国であるにもかかわらず、なぜ使わないのか、という疑問を持つことです。
もちろん、より資材に適した安い素材が海外にあるなど、輸入材を利用している様々な理由があるのですが、ここにCO₂の排出量も加味した上で、どのような選択をするのか考える必要があります。
今後は、現在決算報告を行っているように、CO₂排出量をはじめとする環境対策への報告をする時代になるかもしれません。
そうなってから取り組み出すには遅い、という状況にならないために、試行錯誤しながらであっても、一刻も早く対策を打つ必要があると思います。
園田: 制度が確定するまでは情報を開示したくないと考える企業も少なくありません。しかし、ネットゼロは今後必ず求められる事柄であり、少なくとも現状を報告できなければ取引自体が難しくなるでしょう。つまり、取り組みを先延ばしにすればするほど、リスクが大きくなるのです。
そこで、船場のように高い志を持っている企業と共に成功モデルを構築し、多くの企業が取り組める環境を作っていきたいと思っています。
小泉: 確かにCO₂排出量の算出方法については、まだ発展途上の段階だと言えます。そうした意味でも、船場のような事業会社と、ウフルのようなSIerが共に最適な手法を見つけていくことで、後から続く企業の道筋となると感じました。
本日は貴重なお話をありがとうございました。
無料メルマガ会員に登録しませんか?

現在、デジタルをビジネスに取り込むことで生まれる価値について研究中。IoTに関する様々な情報を取材し、皆様にお届けいたします。