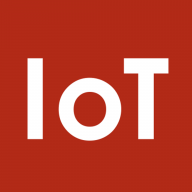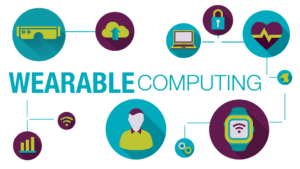将来的には、インターネットに繋がるIoTデバイスは数百億個にもなると言われている。
IoTはバズワードとも言われているが、すでにこの広がりは止めることができない勢いで、世界中の企業が様々なデバイスを世に送り出している。
IoTの未来について考えるとき、目には見えにくい裏側がどうなっていくのか?ということも知っておく必要がある。
今回は、IoTが広がることで起きるクラウド側の問題や、人工知能の話をメインに、シスコシステムズのシスココンサルティングサービス シニアパートナー八子知礼さんに個人的な将来予測についてお話を伺った。
ロングインタビューのため前半と後半に分け、前半はFogコンピューティング、後半は人工知能、ソフトウェア業界とハードウェア業界について、をメインにお届けする。

-シスコシステムズが”IoT”をどういう風にとらえていて、今後どのように発展させていきたいとお考えなのか教えてください。
シスコ全体というと多少話が大きすぎるかもしれませんが、シスコ自体は昔からインターネットを作ってきたという自負がある会社です。パソコンやサーバーが繋がる延長線上でコンピュータ自体がマイクロ化してダウンサイジングしていく中においては、「この先は、もっと小さなものがたくさん繋がってくるだろう」、ということが起きるのは、かなり早くから予測をしていました。
“Internet of Things” という言葉自体は古くからある言葉ですが、それがメジャーに扱われるようになるころには、色々なモノがネットワークに繋がった世界感のイメージは持っていました。それを拡張してモノだけでなく、そこから上がってくるデータとデータの接続、データを業務プロセスの中でリアルタイムに活用していくための業務プロセスの接続、さらに業務の中で人とコミュニケーションもどんどん繋いでいけばシスコのビジネスに繋がると考えていて、全てを繋げること、すなわち、“Internet of Everything”として拡張して提唱してきました。
-八子さん個人としては、IoT、IoEという全体をとらえた時に、どういったところに注目されていて、これからどうなっていくと思われていますか。
ネットワークで接続した先のアプリケーション処理のバックエンドにクラウドを活用する中では、有線のネットワークで繋がっているものが、今までは多かったと言えるでしょう。ところがここ数年で、様々なIoTデバイスとクラウド側バックエンドをモバイルネットワーク、無線で繋ぎ、今までと同じくクラウドで処理しようとすると、無線の帯域が限られているので、モノがどんどん増えるほど、それをさばくのはトラフィックレベルで難しくなってきます。

そして、IoTではきちんと構造化されていないデータが散発的にばらばらと上がってくるという傾向があり、受け取るサーバー側に大きな負荷がかかります。また、動画画像解析などのあまりにも大量のデータ処理や自動運転支援などの超リアルタイムデータ処理が必要になる利用例の場合、クラウドに上げてレスポンスを待つ前までもなく処理をしてしまわなければなりません。
それを簡単な処理やリアルタイム処理であれば、デバイスとクラウド側の中間層で処理してしまいレスポンスも返してしまう、ある程度まとまったところでサーバー側に送るという技術が必要になってきます。
一般にはこのエッジ側で処理しませんか?というコンセプトはエッジ・コンピューティングと呼ばれるものですが、その一つの実現形態として、クラウド(雲)とは反対の地面に近いデバイス側の、コンピューティングということで、我々はFog(霧)コンピューティングと呼んでいます。

これは、基幹ネットワークだと考え方自体は新しくはないのですが、全部がデータセンターサイドのコンピューティングの環境ではなくて、レイヤーごとのある程度の処理、蓄積、バッファということをやらざるを得ない状況がもう起こっているということなのです。
-データ処理をキャッシュするようなイメージですね。
現在世界中にたった10億台強のデータセンター側サーバーしかなくて、そう大きく増えていないという実態がありますが、模式化するためにそのサーバー1台の処理能力を“1”とする場合,クラウド側全部の処理能力は10億となりますよね。一方、デバイスの数は100億台にとどこうかというくらいなので、その処理能力を仮に“0.1”とすると、全デバイス側の処理能力は同じく10億になります。
すなわち、あちら側(クラウド)とこちら側(デバイス)ではほぼ同じくらいの総処理能力だと考えることが出来ます。デバイス側は更に増え続け、クラウドに対してどんどん重い処理を要求するようになりますが、そうなるとクラウド側の処理負荷がオーバーフローしてしまう懸念も出てくるわけです。
もちろん、そうならないようにクラウド事業者はコンピューティングリソースを拡充させますが、投資体力のある事業者は、半導体業界や液晶パネル業界がそうであった様に、いずれ世界で数社に絞り込まれてくることでしょう。
こうしたクラウド側の処理能力のオーバーフローを避け、重要な処理を行う能力に余裕を持たせるためにも、ネットワークの中間ノードにおいても、基本的にはいろいろなモノがコンピュータをベースに設計されているので、この中間のコンピューティングリソースも使って処理させた方が良いのではないか?という発想に自ずとなってきます。

-処理できるものはなるべくある程度の塊で現場側、デバイスに近いところで処理をしていこう、ということですね。
一方でディープラーニングのことを考えると、いらないと思われるデータも全て収集する企業もあります。ビジネスプロセスや、業務処理というのが、はっきりしているものに関して「デバイス側中間レイヤーでもこういう処理をしましょう」というFOGの考え方はすごく有効だと思いますが、「何が起きているかわからない」ということから何かを導き出そうとするディープラーニングの世界からすると、その中間層のレイヤーがある程度データを綺麗に整えてしまうことによって、可能性を損なう、という考えはありませんか?
それはあると思います。ある程度まとまった投資ができて、「何もかも分析するのだ」という意思が働く環境においては、システムリソースや、お金が続く限り、無駄と思われるデータであっても集めて構わないと思います。あとは、本当にそれだけのデータを集めることに投資対効果があるか?ということではないでしょうか?
今はどちらかというと、技術領域の中で興味本位にデータ収集と強化学習行われている傾向が強いと個人的には思っていますが、経験的にそれがある程度蓄積されてくると、結局そのデータを取ったとしても、分析結果に相関性が見いだせないのであれば、意味がない情報を取ってしまっている、ということに気づくフェーズも来るのではないかなとも思います。
そういったことは統計学の専門家もおっしゃっておられますし、このデータとこのデータは明らかに関係ないのに、あえて集めるというのは、「業界別に見た時にこのビジネスにおいて必要ないだろう」というところが早晩、取捨選択されてくる時代も来るのではないかなと考えています。

-シスコシステムズがもともと得意としているインダストリー系の世界であれば、そうだと思いますが、Googleのようにコンシューマー系のところも同じでしょうか。
彼らは、収集したデータを検索や広告に使うというビジネスモデルを作っているので、彼らにとっては、収集するデータこそが広告のネタであり、利益価値の源泉ですよね。Googleなどは、集めることが彼らにとっては通常のオペレーションであり、事業コアなわけです。
一方、他の製造業などの産業の方々からすると、データや情報というのは、オペレーションをしているところから生まれた付帯的な情報です。これら検索や広告ではないビジネスモデルの企業は、どこかで「だいたいわかった」となれば、概ね「これでやっていきましょう」となるかもしれません。とはいえ、未開の地へのグローバル展開やリアルタイムな製造と市場への反応を行うことを強みとしようとすれば、まだまだ多くの、ある意味無駄とも言える情報も集めて分析対象にして経験値を上げていく、ナレッジレベルをあげていかねばならない、ということになると思います。

すなわち、IoTから上がってくるデータの扱われ方については、すべて収集するフェーズの後には事業のドメイン、業界、ビジネスモデルによって取捨選択されていくと思います。我々シスコはストーミングアナリシスというソリューションを持っていて、大量に発生して流れていってしまうデータをなるべくリアルタイムに流れていく中で分析して、異常値やレスポンスすべき傾向が見えたら、すぐに現場にフィードバックを返してしまい、取得したデータは捨ててしまう、というデータ分析の世界観を実現する手段も提供しています。もちろん、すべてがそうなるというわけではないですが。
八子氏へのインタビューは全3回です。
無料メルマガ会員に登録しませんか?
IoTに関する様々な情報を取材し、皆様にお届けいたします。