必要性からスタート、ハードウエアならではのトラブルを乗り越えたJapanTaxi

JapanTaxiの岩田氏は、5年くらい前、タクシー業界ではドライブレコーダーをつけなければならなかった時期に、市販品は高価だったので、コストを抑えたものを作ろうとなったと経緯を振り返る。
0号機では、ドライブレコーダーなのに録画できていないといったトラブルが起きたのだという。(その後、不良品については、1号機と交換した)
これは、SDカードの相性など、ハード的な問題もあったが、問題のある0号機はすでに納品してしまっていたので、1号機までのリードタイムは最短で作る必要があったし、失敗したらハードウエアから撤退することになりかねなかったという。
しかし、車メーカーでの品質へのこだわりがある人材が入社してくれたことで、飛躍的に品質が向上したのだと振り返る。
JapanTaxiも生産は、深セン(JENESIS)だ。JapanTaxiの場合、デバイスはタクシー会社が管理していることもあり、ソフトウエアのアップデートは、起動時に行なえば良いと言うメリットがあったのだという。
プロダクトリリース後の開発に関して、基本はアジャイル開発だという。
最近は電子決済が多いので、そういったビジネス要件によってアップデートしてる。QR決済については問題ないが、非接触デバイスのようなものについてはハード的回収が必要な場合もある。
こういった対応への問題点は、世の中の動きが早くなってきていることだと述べた。
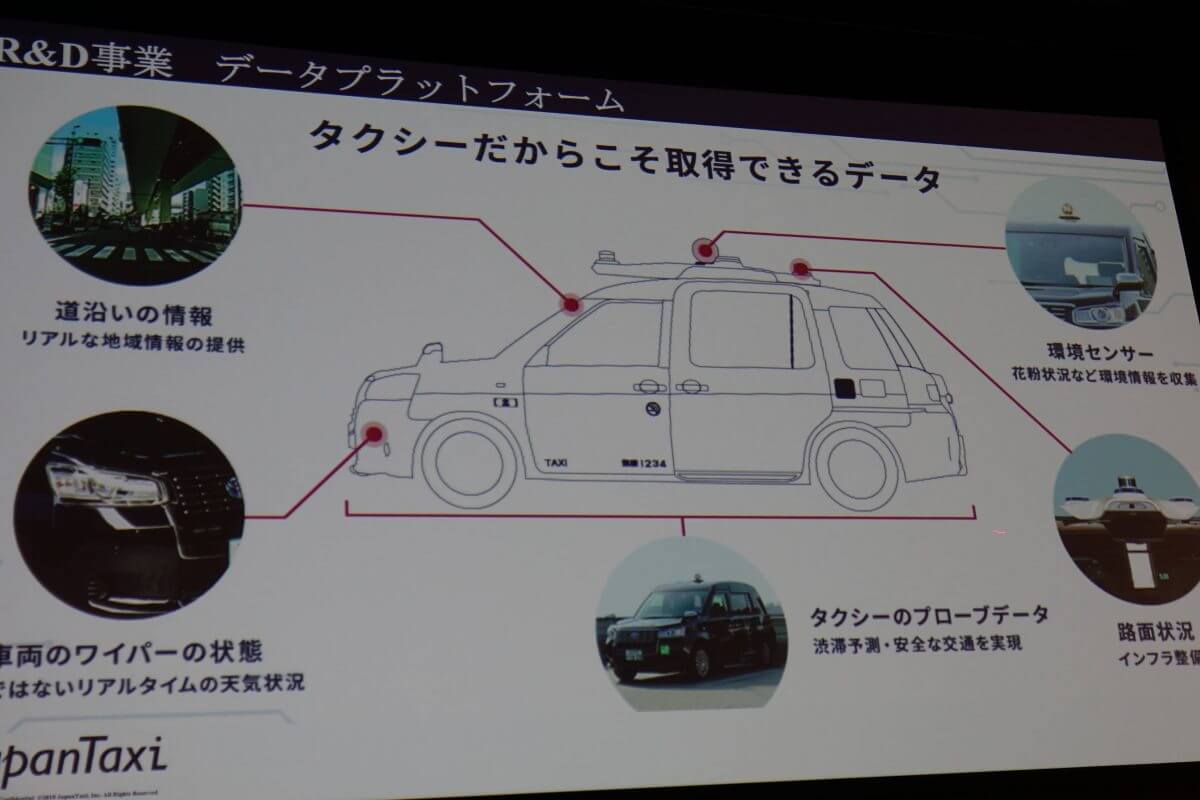
最後に、ハードを扱うのは大変なことだが、リアルなものを作っているというやりがいをメンバーが感じるようになったのだという。
実際、こんなこともつくっちゃうの?というものも作って、「ソフトエウアメーカーとは違った世界がみれるという意味でも、次のことに挑戦をしていきたい」と述べた。
次のページは、「if-up2019を通して」
無料メルマガ会員に登録しませんか?

IoTNEWS代表
1973年生まれ。株式会社アールジーン代表取締役。
フジテレビ Live News α コメンテーター。J-WAVE TOKYO MORNING RADIO 記事解説。など。
大阪大学でニューロコンピューティングを学び、アクセンチュアなどのグローバルコンサルティングファームより現職。
著書に、「2時間でわかる図解IoTビジネス入門(あさ出版)」「顧客ともっとつながる(日経BP)」、YouTubeチャンネルに「小泉耕二の未来大学」がある。




















