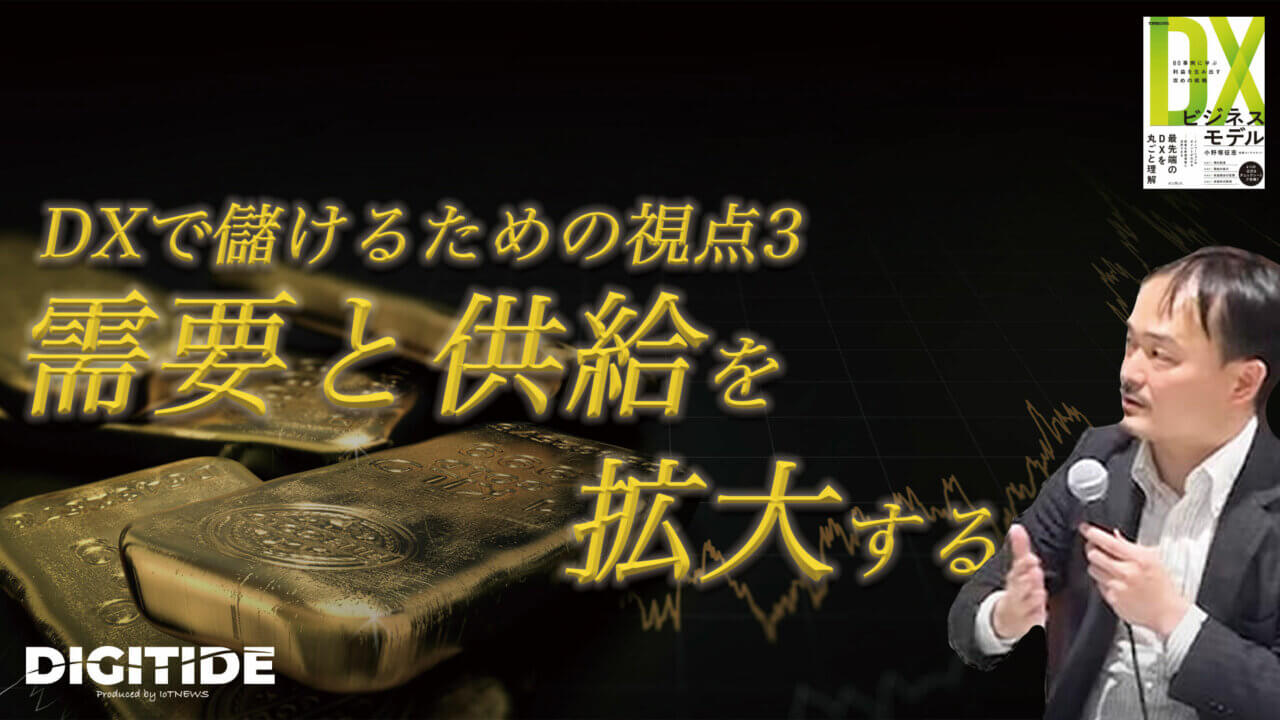DXという言葉を聞かない日はないが、実際、DXをして儲けた企業があるのだろうか?という疑問を持つ人は多い。その疑問に応えるべく、特集「デジタル時代のあたらしい儲け方」では、ローランド・ベルガー パートナーの小野塚征志氏とIoTNEWS代表の小泉耕二が対談した。
特集「デジタル時代のあたらしい儲け方」は全八回で、今回は第六回目、DXで儲けるための4つの視点の三つ目の視点である、「需要と供給を拡大する」がテーマだ。
小野塚氏は、慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科修了。日系シンクタンク、システムインテグレーターを経て、現在、ローランド・ベルガーでパートナーを務める。2022年5月19日には「DXビジネスモデル 80事例に学ぶ利益を生み出す攻めの戦略」を上梓した。
ローランド・ベルガーは、戦略系のコンサルティング会社。企業の中期経営計画の策定、企業の買収、リストラなど、企業が経営戦略でな大きな意思決定を行う際のサポートを行っている。
IoTNEWS 小泉耕二(以下、小泉): 3つ目の「需要と供給を拡大する」はどのような内容でしょうか?
ローランド・ベルガー 小野塚征志氏(以下、小野塚): 一番分かりやすいのは、前に挙げた民泊の例(第3回)です。要は「使われなくて眠っている資本や資産があるのではないか」という視点です。
家の駐車場を有効活用するakippa
この本の中でいうと、「akippa(アキッパ)」という日本のベンチャーが行う駐車場の事例があります。
例えば、駐車場付きの一軒家を建てた後に、「あまり乗らないから」と車を売る人がいます。そうすると駐車場は空(あ)いた状態になりますよね。でも、もし家のそばに野球場があって、土日は近くの駐車場が満杯になるとします。そうしたら、家の駐車場を貸せたらいいですよね。
そういうときに真っ先に浮かぶのはタイムズです。しかし、タイムズで駐車場を提供する場合には、車止めや看板を設置する必要があり、費用が結構かかります。かかった費用以上に利用率が高そうだと見込まれるならやってもいいかもしれません。
しかし、駐車場が家の軒先であればスペースは限られてしまいます。そこで、akippaでは、車止めや看板といった設備を設置することなく、駐車場の空きスペースを提供できるサービスを行っているのです。
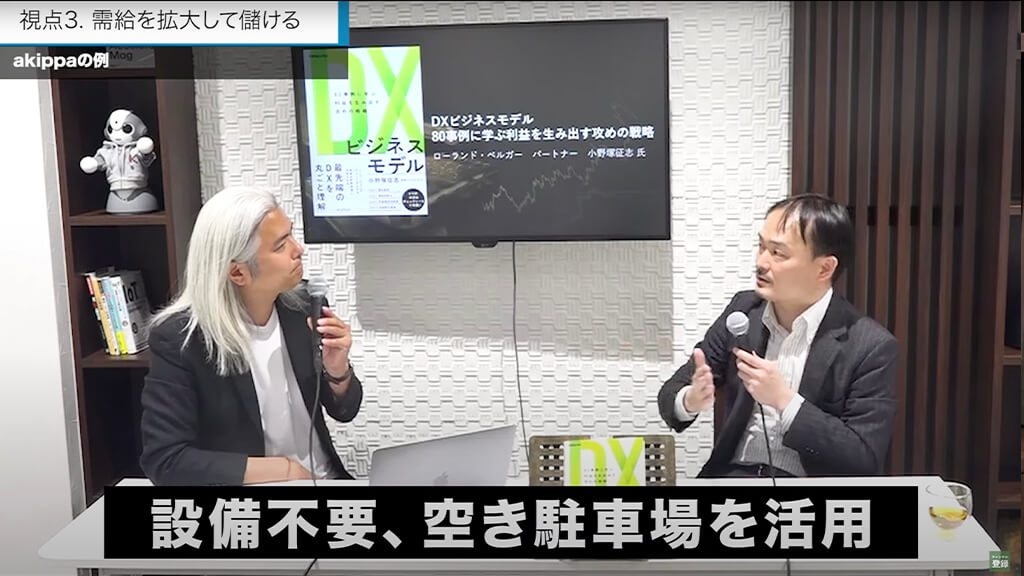
具体的には、空いている駐車場を保有している人は、氏名や電話番号、駐車場の所在地やサイズなどの情報をakippaに登録します。一方、駐車場を使いたい人はakippaに車のナンバーや車種などを登録した上で、アプリで駐車場を検索し、予約をします。
予約した車は、予約時間内に駐車をすることができます。そして、駐車場を貸し出した人は予約車以外で不正利用している車を特定することも可能です。駐車料はアプリを通じて支払われます。そのため、精算機などを設置する必要がないのです。

akippaでは、曜日や時間帯を指定して貸し出すこともできます。平日は会社に車を置いていて空いているので、平日だけ駐車場を貸し出すといったことも可能です。設備はいらないですし、時間単位で貸すことができるわけです。
このビジネスは貸し手が、駐車場で、確実におカネを儲けることができます。使う側からしても、もしかしたら安く駐車できるというメリットに加え、駐車場を探す手間が要らなくなります。
今までだったらデパートに車で行った場合、駐車場が混んでいたら、車を止めるために並ばなければいけませんでした。そして、駐車場が満車とわかったら空いている駐車場を探すというステップが必要でした。
それが、akippaであれば予約することで、そういうときでも確実に予約した時間と場所に駐車することができるわけです。そうなると、駐車場は予約して行くのが当たり前になるかもしれません。供給側も、新しくおカネを儲ける機会が生まれます。
小泉: akippaの場合は、登録して空いているスペースを貸すだけでよいのですね?
小野塚: そうです。そして、これも高度なテクノロジーは活用していません。駐車場の場所をGPSに表示できるようにして、写真を撮って登録してもらい、管理をすればよいだけです。
ものすごく複雑な手続きや処理が必要なわけではなく、高度な機材がないとできないものでもありません。これは発想を変えることで、需要が増やせるかもしれないという事例になります。
小泉: こうしたサービスはやった者勝ちなのでしょうか。それとも先にやった人がいても、違う人が始めたらそれはそれで勝ち見込みがあるものなのですか?
小野塚: もちろん最終的には、何社かに絞られてくると思います。例えば、コンビニにしても最終的には何社かに絞られているように、淘汰される可能性は出てくると思います。
だから、先行者であることは非常に重要で、早めに始めた方が有利に働く場合が多い。ベンチマークするために上手くいっている会社があるかを気にする人も多いですが、うまくいっている会社が、すでにあったら、二番煎じになる可能性が高いということなのです。
小泉: 空いているスペースを提供してほしいというサービスなのに、上手くいっているところがあったら、やる気がなくなりますよね。
DXで大切なのは「千三つ」の挑戦
小野塚: ただ、チャレンジすることは大事です。akippaのケースでは、駐車場の持ち主が多くの投資を必要としないと説明しました。一方で、akippaという会社自体も、多くの設備投資や高度な技術が必要だったわけではないのです。
それならば、とにかくトライすることが重要です。よくベンチャーでは「千三つ(1000回中で3回の成功率)」と言われますが、DXにおいても「千三つ」です。997回は失敗するので、高速で失敗して、上手くいかなければ辞めて次の施策に変えればいい。多くの投資が必要ではないので、とにかくトライをしてみて、ちょっと上手くいったらそれを広げていく行動力が重要なのです。
小泉:日本の大企業が苦手なことですね(笑)。
小野塚: 逆に言うと、起業家を目指したい人には、すごいチャンスだと思います。

小泉: ただ、空いているスペースや資産は、見回してみてもそこまでたくさんある感じがしないのですが、チャンスはまだあるものなのでしょうか?
小野塚: まだまだあると思います。前に話した「職人と工事会社」(第3回)や「花」(第5回)の事例のように、よく考えたら、間にあるムダなものがあるはずです。あるいは自分や会社が持っていて、たまにしか使ってないなというものは、ほかにもあるのではないかと考えてみると、見つかるかもしれません。
小泉: 社用車が使われずに並んでいるのをよく見かけるので、社用車をレンタカーにしたらいいのではないかと、今思いました。今回の視点は、「たくさんある割には使ってないな」というものを見つけて、これを時間で貸してみてはどうだろうという発想がスタートになるということなのですね。(第7回に続く)
この対談の動画はこちら
以下動画の目次 8.視点3: 需要と供給を拡大して儲ける(48:01〜)より
無料メルマガ会員に登録しませんか?

IoTに関する様々な情報を取材し、皆様にお届けいたします。